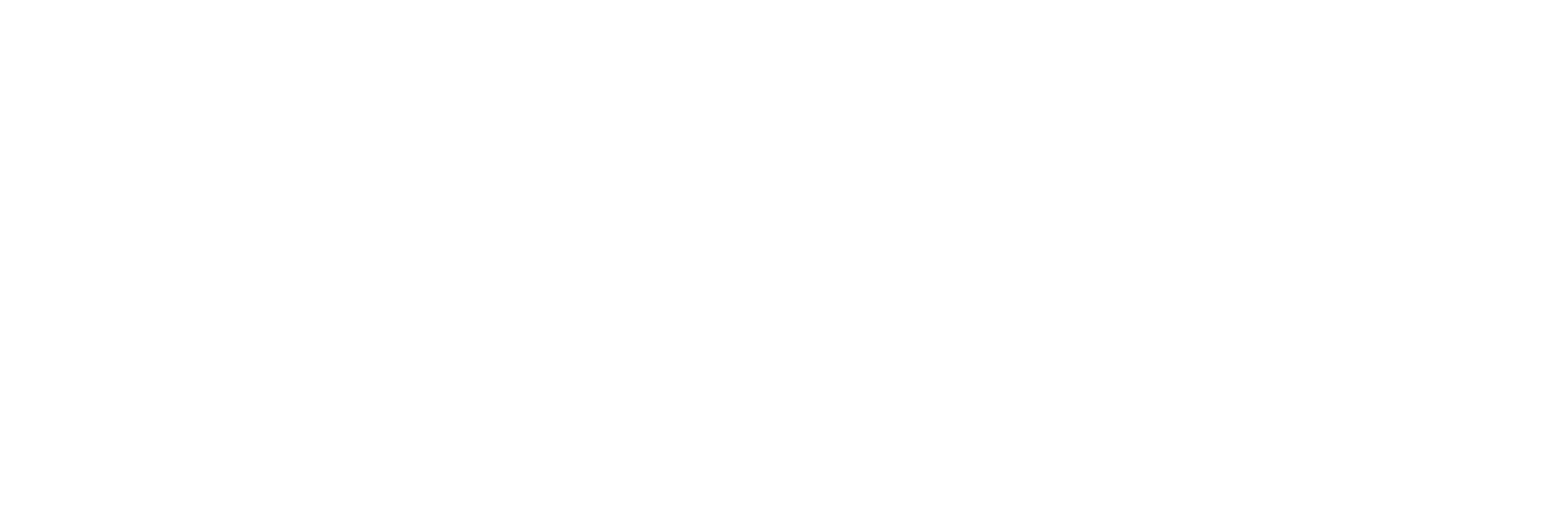「噛めば噛むほど愛が膨らむ」のキャッチコピーで売り出されたチューインガム「LOVE」は、全世界からお菓子好きが訪れるお菓子の国ロテコきっての大人気商品だった。
その中の一枚である、そのガムは、自らが愛にまつわる存在として生産されたことを誇りに思っていた。そして、ロテコ国民が祀っているお菓子の神様を自身も心から崇拝していた。朝と昼と夜に三度、神様へのお祈りを捧げるのがそのガムの日課だった。
どうか駄菓子と呼ぶことなかれ、愛は世界を救うのです。
ガムはしかし慎重に町を旅した。チャンスはたった一度きり、誰かに噛まれたら、もう他のひとの口の中に入ることはなかろう(それは生理的に受け入れがたいに違いない)。噛めば噛むほど愛が膨らむというのが自分だが、どうせなら自分を必要としてくれる相手にこそ愛されたい。焼き肉屋で下品な大笑いをしながら適当な酒を飲んだ大金持ちの口直しに噛まれるのなんかまっぴらごめんだ。崇拝する神様がお創りになられた存在なのだから自分はある程度は素晴らしい存在であるはずだと思いながらも、ガムはそれでいて、自分がたかだか一枚のガムでしかないこともしっかり理解していたのだ。
・・・・・・・・・・・・
お菓子屋を見渡していても一向に運命の相手は見つからなかった。ビル街をうろつき、公園をうろついても、自分の運命の相手は見つからない、仕方がないので飲み屋なんか覗いてみたり、工事現場なんかに忍び込んでみても見つからない。地上のどこを探してもダメだったもので、ガムは神様にお祈りをしながら、ままよ! と、マンホールの隙間からポトリと落ちて、地下道に降り立った。
薄暗い中を進むと、啜り泣きが聞こえた。声のするほうの暗がりに目を凝らすと、1匹のネズミが泣いていた。
ガムはネズミに話しかけた。
「ネズミさん、どうしてそんなに泣いてるのですか?」
ネズミは自分の家族のこと、これまでにあった悲しいこと、いままさに独りぼっちで途方に暮れてしまってることをガムに話した。それらは悲しみに満ち溢れた壮絶な物語だったもので、ガムはこのネズミのことを幸せにしたいと心から思った。
「そうでしたら、この僕をパクリと口に入れて、くちゃくちゃと噛んでごらんなさい。たちまちに良いことが起こりますよ?」
ネズミはぐすりぐすりと涙に濡れた目を手でこすりながら、その体にしてはずいぶんと大きな口を開けて、ガムを噛んだ。ひと噛み、ふた噛みと繰り返し噛み続けるうちに、さっきまで泣いていたネズミの表情は瞬く間に明るく輝いていった。もちろん、ネズミの口の中に入ってしまったガムにはそんな様子は見えないのだが、ネズミが「おいしいおいしい」と弾むような声で繰り返すものだから、それを聞くだけでガムはうっとり、幸せになってしまった。ガムは、この世界に創られたことはとんでもない幸運だったと心から思い、お菓子の神様に感謝した。
「おいしい、おいしい!」
「そうでしょう、そうでしょう!」
ネズミは一晩中ガムを噛み続けた。地下道の壊れたライトが、まるで星屑のように点滅していた。
・・・・・・・・・・・・・・・
「さ、もう吐き出してくださいな。あなたに噛まれたことは僕の幸運でした。」
朝になるとガムはネズミに向かって言った。しかし、ネズミは慌てて断った。
「いやだよ、もっと噛んでいることにする」
「なんですって?」
「なんだかとってもいいあんばいなんだ。ずっと噛み続けていたい。それでもいい?」
「そんなの・・・もちろんさ」
ガムは内心とっても嬉しかった。実のところ、ガムの方でも、そうであったらいいなと思っていたのだ。
次の日になっても、次の週になっても、次の月になっても、なんと次の年になってもネズミはガムを噛み続けたのだった。ふたりはもう、まるで大昔から一緒にいたのが当たり前みたいで、終始笑って過ごした。ガムとネズミはお互いの身の上話や考えをたくさん話したもので、いつしか、お互いに知らないことはないくらいになっていた。
「この国で一番人気な君を噛むことができてとってもラッキーだなあ。本当に本当においしいガムだ」
ネズミが上機嫌で言うと、ガムの方は胸の内側をくすぐられたみたいに嬉しくなって、
「まあ、噛みたいだけ噛み続けたらいいさ。僕はスーパーマーケットでも品切れが相次ぐような上等なお菓子なんですからね。」
と威張るのだった。
それからもっと長い時間が過ぎたある日、ネズミが言った。
「ねえ、この国から離れて暮らさない? 前にね、花が咲き誇る国があるって聞いたことがあるんだ。ネズミの命はとても短いらしくてね、どうにかして、生きているうちにその国に行ってみたいんだよ」
ガムは言葉を濁した。
「良い提案だけれど、果たしてわざわざ今すぐに行くだけの価値があるものかしら? 毎日、こんなに忙しいというんだから、うん、いつか落ち着いて考えられるときに、行くかどうかしっかり検討することにしよう。」
忙しいのは本当のことだった。ガムは毎日朝から晩までお祈りをし続けた。前は日に三度だったが、ネズミと出会って以来、ガムは随分と調子が良くなってしまって、日がな一日、「あー大変、もっとやらなくちゃ、もっとやらなくちゃ」とバタバタとお祈りをしているのだった。
その日から、ガムとネズミはときたまケンカをするようになった。喧嘩が続くとネズミは泣きだしてしまい、そうなるとガムはどうしたらいいのかわからない。自分が無力な気がして不機嫌になってしまうのだった。
ネズミはいつだってガムのことをくちゃくちゃと噛み続けてくれていたものだから、ガムはもう十分に満足だった。それだのに、ネズミときたら折を見ては、「花の国に行きたい」という話をするもので、ガムはそんなときには思わずムッとしてしまうのだった。
本当のことを言えば、ガムはお菓子の国から離れるのが怖かったのだ。
お菓子の神様にお祈りして手に入れた今の毎日を変えでもしたら、とんでもないことになってしまうかも知れないという不安でいっぱいで、ガムは「不安を消してください不安を消してください」と日々お祈りを続けた。いつか安心できたら、その時こそ花の国に行きたいと思っていた。花の国に行くことは、それはそれでとても楽しみだった。それならそうとネズミに言えればいいのに、ガムの自尊心が、ネズミの前で情けない姿を見せたくないと頑なに拒んだ。
どうしてネズミは待てないのだろう?
ガムはもっとネズミに幸せそうにしていてほしかった。
自分は「噛めば噛むほど愛しちゃう」はずだのに、なぜネズミはここのところ、またよく泣き出すようになってしまったのだろう。
・・・・・・・・・・
ある晩、ネズミはまた泣き出した。
「泣くのやめてくれませんか?」
ガムは叱りつけるような口調でネズミに言った。ネズミはより一層大きな声で泣き始め、ついには大きな声でわんわんと泣き出した。ガムは今日こそはわかってもらわないわけにはいかないぞと、心を決めて話し合おうと思った。つい口調が強くなってしまい、しまった、と自分でも思っていたけれど、一度口に出すと勢いが止まらなくなってしまった。
「いいですか?僕はただただ、あなたを幸せにするためにあなたの口の中に飛び込んであげたわけです。いますぐ花の咲く国に行きたいあなたの気持ちはわかりますけど、でも、ぼくがここに今その余裕がないことも知ってほしい。僕は不安で不安で仕方がないんですよ。そんな話も聞いてくれないだなんて、君は少々、自分のことばかり考えているんじゃないですか?」
ネズミは泣きながら言い換えした。
「聞いてほしいことがあったなんて、言ってくれなきゃわからない・・・」
「君がいつも自分のことばかり話して泣いてばかりいるから、僕は言えなかったんですよ。」
ネズミはもうわけがわからないくらいに大泣きをしだし、しゃくりあげながら話した。
「初めて会った時、君を噛んで涙が止まった。それからね、どうしても君を幸せにしたいと願い続けてしまったんだ。」
ガムは驚いて息が止まった。まさかネズミがそんなことを考えていただなんて考えもしなかったのだ。
「・・・ちょっと待ってよ、ネズミ、君は・・・」
「君を不幸にしたのなら耐えられない」
悲しさのあまり大泣きしたネズミは目からポロポロと涙を流し、嗚咽と一緒にガムを吐き出してしまった。
ぼちゃ
ガムは地下道を流れる下水におち、濁流に飲み込まれた。がんばって這い上がれないこともなかったのだが、「どうにでもなれ」とそのままどこかへ運ばれていってしまった。
翌朝、ガムはどうにか下水の岸辺に這い上がると、うなだれ、ひどく悔やんだ。
ずいぶんと遠くまで流されてきてしまった。ネズミの口の外に出たのも、一人ぼっちでいるのもずいぶんと久しぶりのことだった。そうなってみると、何をしたいのか、何をしてよいのかもわからなくなっていた。
自分は昨晩、どうしてあんなに腹が立っていたのだろう?
思い出そうとしても無理だった。一体ネズミがどんな悪いことをしたのだろうか。ネズミが泣き出したのは、いったいなぜだったろうか。
この数年、どんなご馳走にも目もくれずにガムを頬張り続けてくれていたネズミは、日に日に痩せていった。朝から晩までお祈りだなんだと忙しそうにするガムのために、なるべく静かな場所を見つけては邪魔をしないようにもしてくれた。
考えてみれば、ガムには、もう味などなかった。
とっくに吐き出せばよかったのに、ネズミは「おいしいおいしい」と言い続け、ガムのことを噛み続けた。そしてそのたびにガムはうっとり、心を踊らせて喜んだのである。
昨晩のネズミの言葉が頭の中で繰り返される。
「初めて会った時、君を噛んで涙が止まった。それからね、どうしても君を幸せにしたいと願い続けてしまったんだ。」
会いたい。そう思うと、ガムはついに、涙が止まらなくなってしまった。
「噛めば噛むほど愛が膨らむ」
――膨らんでいたのは、自分の愛だった。噛まれるほどに、噛まれるほどに、ガムはもう、ネズミなしでは居ても立っていられない自分になっていったのだ。守られ救われ続けていたのは、自分のほうだったのだ、そう気付いて、ガムは唖然とした。
ガムは、ネズミと過ごした日々のことを思い出した。
あまりに幸せな日々だった。そのひとつひとつが、永遠に続けばいいと思えるものだった。そして、遠い将来、ふたりで思い出したいと思えるものだった。
そしてガムはネズミが泣いている姿を思い出して、胸がえぐられるような後悔に襲われた。
そもそもが、ネズミのすすり泣く姿をみて、このネズミに噛まれようと心に決めたガムだった。守りたい気持ちだったのだ。
――すべてを謝って、ネズミと一緒に、花の咲く国に旅に出よう。
そう決めてみると、それはなんだかとても素敵なことのように思えてきて、ガムは嬉しくなった。
ガムは大慌てで元の地下道に戻ることにしたが、ずいぶんと遠くまで流されてしまっていたらしく、簡単には戻れなかった。それでも何日も何日もかけてようやくのことでお菓子の国の地下道に辿り着いた。
しかし、必死で探しても探しても、ネズミはもう見つからなかった。
――花の国に行ったら会えるかもしれない
そう考えてガムは旅に出たけれど、半日もしないうちに道端で力尽き、ぱたりべったり、地面にへばりついてしまった。
ガムはおもった。
――もう一度あの頃に戻りたいな。
「いますぐ、動物の国に行きたいです。ネズミに会わせてください。」
ガムはお菓子の神様に祈り続けた。
ガムの体は次第に固くなり、石のようになっていった。
そのうえをたくさんの人間や動物が踏みつけて歩くものだから、ガムは真っ黒になった。
ガムというやつ、あれでなかなか丈夫だもんで,にわかに朽ち果てるという性質がない。
そのまま固くなって、岩のように、永遠に張り付いてなければいけないらしい。
もはやそれがお菓子の国ロテコで大人気だったガムだなんて、誰一人気が付かないのだった。
「いますぐ、動物の国に行きたいです。ネズミに会わせてください。」
ガムはいつまでもいつまでも、お菓子の神様に祈り続けた。


2024/09/15 00:34