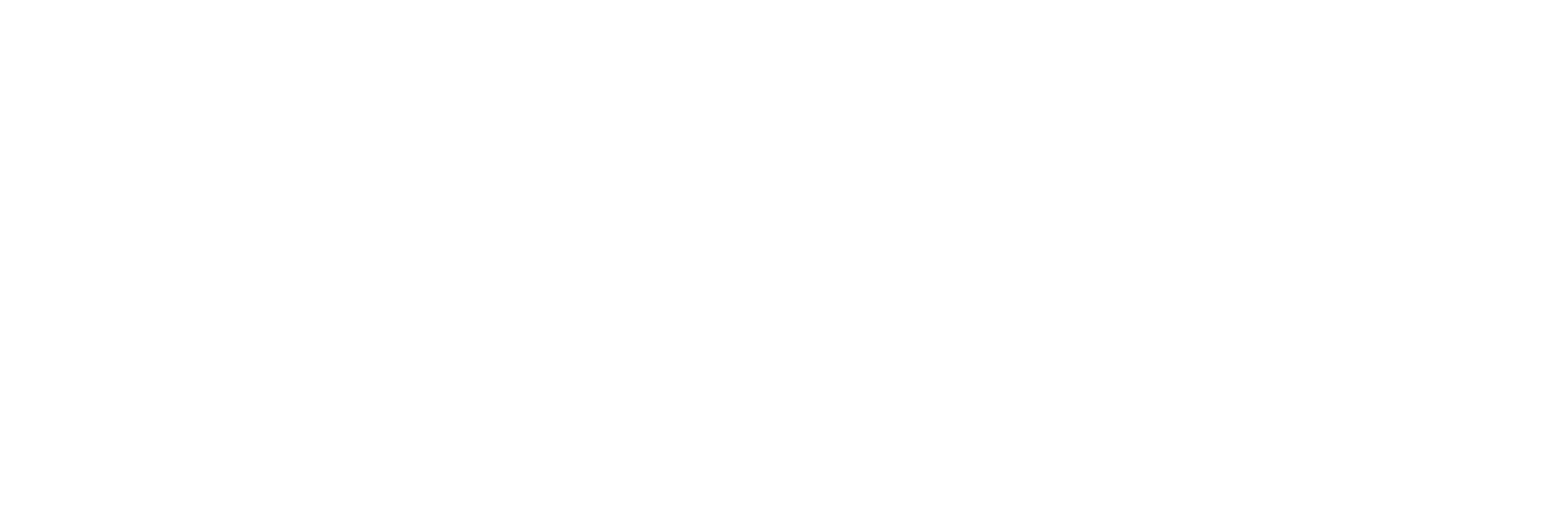思い出狩りのハシビロコウ
「レストランに突然おかしな様子のハシビロコウが入ってきたものだからその場にいた全員はギャっと叫んだ。人がなぜ驚いた時に叫ぶのかはわからないが、きっと、叫ぶことによって相手を威嚇したい、というような意味合いもあるのだろう。なるほど確かに、レストラン中の全員が同時にハシビロコウに気が付き、同時にあげた「ギャっ!」という叫び声は大したボリューム感と刃物のような切実さを孕んでいたものだが、ああ、どういうことだろう、ハシビロコウの奴は、びくりともしなかったんだ。」
おしゃべりなテナガザルは得意げに語っていた。そこに居合わせたテナガザル一家の3匹たちは、ふんふんと、その話に聞き入っていた。同じ種族として生まれたのに、どうしてこいつはこうも話が上手いのか、3匹はいつだって感心していた。今夜も、何か面白い話をしてくれないか、と頼み込んだのだ。
そのうち猿たちは口々に質問した。父ザルに次いで母ザルが、母ザルに次いで、子ザルが。
「ハシビロコウは、なぜ、びくりともしなかったんだい?」
「人間がいるだけでも普通は警戒するものでしょう」
「しかも、ギャっ!という声は相当に大きかったんだよね??」
「さあね、余程に肝が座っていたのか、もしくは・・・探し物に熱中していたんだろうね。」
「探し物?」
「みんなが叫ぶとすぐに、ハシビロコウは、その大きい翼をこう、サッと掲げて、言ったそうだ。・・・どうぞお気になさらないでください。私は、私の思い出を探しているだけで、あなた方に危害を加えるとか、他に、何か悪いことをしようなどとは、一切考えておりませんので・・・」
「思い出を探している?」
「ああ、そう言ったらしい」
「思い出なら、自分の体の中に収めておくべきもんだろ?」
「ハシビロコウは、なんだってレストランなんかを探していたの?」
「それにさ、探してどうするつもりだってんだろう??」
テナガザルたちがやいのやいのと騒ぎ立てると、おしゃべりテナガザルはその反応が欲しかったとばかり、得意げに、指をぴーんと立てる。サルたち沈黙。ニヤリと笑うおしゃべり。そして、続く、おしゃべり。
「お前らが今言ったみたいなことを、そこにいた全員が口々にハシビロコウに投げかけた。ハシビロコウのやつ、探し物に夢中だからか最初は地面キョロキョロしながら無視してたんだが、やがて騒ぐ奴らを煩わしく思ったんだろう。顔を上げるとギロッと・・・なあ、わかるだろ?あの目だよ、あの目で、そこにいる全員をギロっと睨んで・・・まあ、意図的に睨んだのか、目つきの問題でそうなっちまったのかは知らねえけどよ・・・」
「あー、話が長い!いいんだよ、ディテールはそこそこに飛ばしてでいいからよ、ハシビロコウがなんで思い出を探していたのかを教えてくれよ!みんなを睨んで、で?なんて喋ったんだよ!」
「なんだその口の利き方は!」
「うるさいおしゃべり!いいから続きを話せってんだよ!いちいち周りくどい言い方ばっかするからお前はずーとひとりもんなんだよ!」
「ちょっとあんた!!」
女房に叱られて父ザルは思わずハッと口を抑えた。
「いや・・・おしゃべり、つい言いすぎた。ごめん。続きを聞かせてくれよ。今のは、言いすぎた、忘れてくれ。」
このおしゃべりテナガザル、話がうまいので人気もあるのだが、実は妙な噂があったもんで、サルのくせにサルには興味がなく、他の種族と交流をする趣向があるという。少し気持ちの悪いところだが、その気持ち悪さが、彼の語る言葉を一層輝かせたのは事実だった。
おしゃべりテナガザルは立ち上がり、3匹の猿たちから距離を取ると、おかしな格好で立ち、腕を広げた。猿たちははじめ意味がわからなかったが、やがてそれは、サルなりにハシビロコウの姿を真似ているのだなと気付いた。サルなりなハシビロコウは、芝居がかった様子で妙な声色でもってハシビロコウの言葉を語り始めた。
「私は、前に、自分の中にある思い出をみんなバラまいちまったんです。」
テナガザルたちは驚き、悲鳴を上げた。
「思い出をばら撒く!?一体どうしてそんなことを!」
「わかりませんね、その理由を教えてくれる思い出も、一緒にばら撒いちまったんですから。だけれど何か、とっても重要なことがあたしの身に起きて、私は、癇癪でも起こしたんですかね、みーんなばら撒いちまったようです。そこからは覚えていますよ。思い出をばら撒いちまった!って、ここから先のことは、ちゃんと、この胸の中に、残酷な思い出としてしまっておりますから。いやー、ばらまいた瞬間は、気分がスッとしたもんです。体が軽くなる感じと言いますか、なんか、こう、救われるような・・・。」
「あんたの体から放たれた思い出たちは、どうなったんで??」
「飛んで行きましたよ、ビューン!と、世界中のあちこちに。海の方へ向かったものもあるし、空を泳いで行ったものもある、狭い裏路地を蛇のように這っていったものもある・・・それぞれ、それぞれです。」
「まあ、それはそうだわ。思い出たちだって、それぞれ大事に大事に生まれてきたんだもの。それぞれの気持ちや感情や、考え方があるわよね。」
「そうなのでしょうね。嬉しそうにとっとと行っちまうやつもあれば、名残惜しそうに私の近くでふわふわ飛んでいるもの、気遣っているのか、私にまとわりついてくるような思い出もありました。でもね、私は、そいつらを放ってスッキリしているところでしたからね、しっしっ!と手を振って追い払ってやりました。それでもしつこい奴には、やっ!!と叫んでみたりね・・・ほら、私、目つきがこんなでしょ?強く睨むと、みんな怯んで逃げていくんです。思い出たちも・・・そうでした」
「へー・・・。思い出が自分の中で溶けて死んじまうことはままあるにせよ、自分の外に思い出を捨てっちまうだなんて、聞いたことないぜ」
「でも、ハシビロコウ?あなた、そんなにスッキリしたならどうして思い出なんか探しているの?」
「ねえ、なんでなの??」
ハシビロコウ役として芝居をしていたテナガザルはぴくりと固まった。大きく広げていた両の手をスッと手を下ろすと、近くの岩に腰掛けた。話に聞き入っていたテナガザルたちは、またおしゃべりテナガザルがじらして話を盛り上げようとしいるのかと思っていろめきだった。しかし、おしゃべりの顔を見るとどうやら違った。おしゃべりテナガザルは、小さな声で話の続きを始めた。
「レストランでハシビロコウが話したのは、こうだ。思い出たちをみんな追い出して身軽になったハシビロコウは、意気揚々と毎日を過ごし始めたらしい。新しい思い出を少しずつ集め、身軽になった体を翼で浮かせて大空だって飛び回ってたらしい。たまに嫌な思い出ができると、今度はもう溜め込みもしない、例によって、ビューン!って、どっかに向かって飛ばしちまうってんだ。」
「へー、まあ、そんなことできるのか。確かに、それはいいかもなあ」
「だから、じゃあハシビロコウは、なんだって昔の思い出探してるのよ!」
「探すの、大変じゃん!」
「・・・再会しちまったことが、あるらしいんだ。」
「え?それって・・・放り捨てた、自分の思い出と、ってこと?」
「そ。まあ、ハシビロコウから逃げ出した思い出たちは、世界中を飛び回ってるわけだからさ、滅多にないことかもしれないが、ふとした偶然で、ばったり出会しちまうことも、まあ・・・あるにはある・・・あったらしいんだよ。」
「それでそれで?どうだったんだよ。だって、ハシビロコウは、その思い出のことなんか忘れ切っちまってるってことだろ?」
「そんなような質問が、レストランでもハシビロコウに投げかけられた。そしたらよ、ハシビロコウのやつ・・・泣き出しちまったんだそうだ」
「え?」
「思い出したくない、思い出との再会のことを、思い出したくない、って」
「お、おい、何があったんだよ」
「ハシビロコウが思い出たちを捨てたのは、それがどうしようもなく苦しい思い出だったからということ?」
「でもだったらさ、その、思い出と再会したていう思い出も、また捨てちまえばいいんじゃない??」
「捨てたくない、んだってさ」
「何?」
「大切な、大切な思い出だったらしいんだ。大切に思っていた相手との、大切な思い出。だけどさ、思い出なんて、未来に続くから美しいもんだろ?続いた先の未来で思い出すから、美しく感じるものだろ?どこから思い出すかが、大事なんだ。だろ?・・・ハシビロコウとその相手には、幸せな未来は訪れなかった。だから、ハシビロコウのやつは、その思い出全部、捨てちまうことにしたんだそうだ。でも、残酷な運命がその思い出とハシビロコウを再び引き合わせたとき、ハシビロコウはその思い出自体が、あまりに美しいことに気付き・・・」
「いい話だな!そうか、それで、一度捨ててしまった思い出たちを全部、また探そうって気になったってことか!」
「違う。全部の思い出を捕まえ直して、その思い出たちみんな、みんな、殺しちまおうって決めたらしい」
「・・・は?」
「どゆこと?」
「思い出を、殺しちゃう?」
「そのハシビロコウは、思い出殺しのための機械を常に持ち歩いてるんだってさ」
「そんなものあるの?」
「ないわよ」
「頭おかしいんじゃないの?」
「さあ、どうだろな」
「で、でも、なんで、せっかく美しい思い出を殺しちまうんだよ」
「ほんと!大切にすればいいのに」
「で、そこのレストランには、探していた思い出はあったの?」
「なかったってさ。ハシビロコウはがっかりして、そこにいる全員に謝ると、店を出た。」
「・・・それでまた、旅を続けるのか」
「美しい大切な思い出を探して?」
「妄想の殺し機械を携帯して?」
「バキューン!」
「え?何の音?」
「唐突すぎるわ。」
「ねえ、どうしたの?」
「銃声。ハシビロコウが店の外に出るなり、銃声が鳴り響いた。・・・やつは撃たれて、倒れて・・・息たえた。たまたまそこに、猟師がいたんだそうだ。」
「えーーー!!」
「まじかよ!」
「旅の終わりかあ。」
「ああ、そして、猟師はすぐにレストランの厨房にハシビロコウの死体を引きずって行って、料理長に売り払っちまったってさ。その日の特別メニュー、“思い出探しのハシビロコウのソテー”を客たちはみな珍しさに大喜びして注文したが・・・あまりうまくはなかった、て話さ。」
「・・・なんだか切ない話だな。」
「よくわからないわ」
「ねえ、それって、作り話?」
「さあ。」
「なんだか、いっつもあんたがしてくれる話に比べて微妙だな」
「なんで今夜はこんなお話だったの?」
「子供向けじゃないと思う!」
「そうだな、申し訳ない。うっかりしたよ。入りたてほやほやの話だったもので、試しに、試しにさ、話してみた。」
「そうなのか!え?じゃあ、これ、作り話じゃないの?」
「さあ、どうだろな。いやいや、今夜は、話を聞いてくれて嬉しかったよ。普段の夜は、独り退屈に過ごすもんだからな」
「家族は持たないのか?家族はいいぞ!幸せだ!」
「あらやだ、あなた。」
「ねえ、僕もう眠いよ。」
「またいつでも遊びに来てくれな。さ、おやすみなさい。」
「ああ、おやすみ!」
「遅くまでお邪魔しました。」
テナガザルの親子は歩き始めた。と、子ザルが立ち止まり、おしゃべりテナガザルにむかって尋ねた。
「ねえ、あのさ、ハシビロコウの思い出は、なんの思い出だったの?」
「え?」
「さっき、大切な相手との大切な思い出だと言ってたけど、大切な相手ってだれ?なんで、ハシビロコウとその相手の誰かには、未来が訪れなかったの??」
一瞬、おしゃべりテナガザルは固まった。饒舌な彼らしくない沈黙を子ザルは不思議に思ったが、さっとおしゃべりテナガザルのところに戻り、その腰あたりを抱きしめた。おしゃべりテナガザルは子ザルの頭を撫でた。
「さあ。なんでだろうね。さ、坊主、とっとと帰って寝な!父ちゃんと母ちゃんに置いてかれるぞ!」
そう言うとすぐに子ザルを引きがし、くるっと後ろを振り向いて扉を閉めてしまった。「あれ?」と子ザルは不思議に思った。今、チラと見たおしゃべりテナガザルの目から涙が流れていたような気がしたからだ。
子ザルは急いで、両親を追いかけて行った。