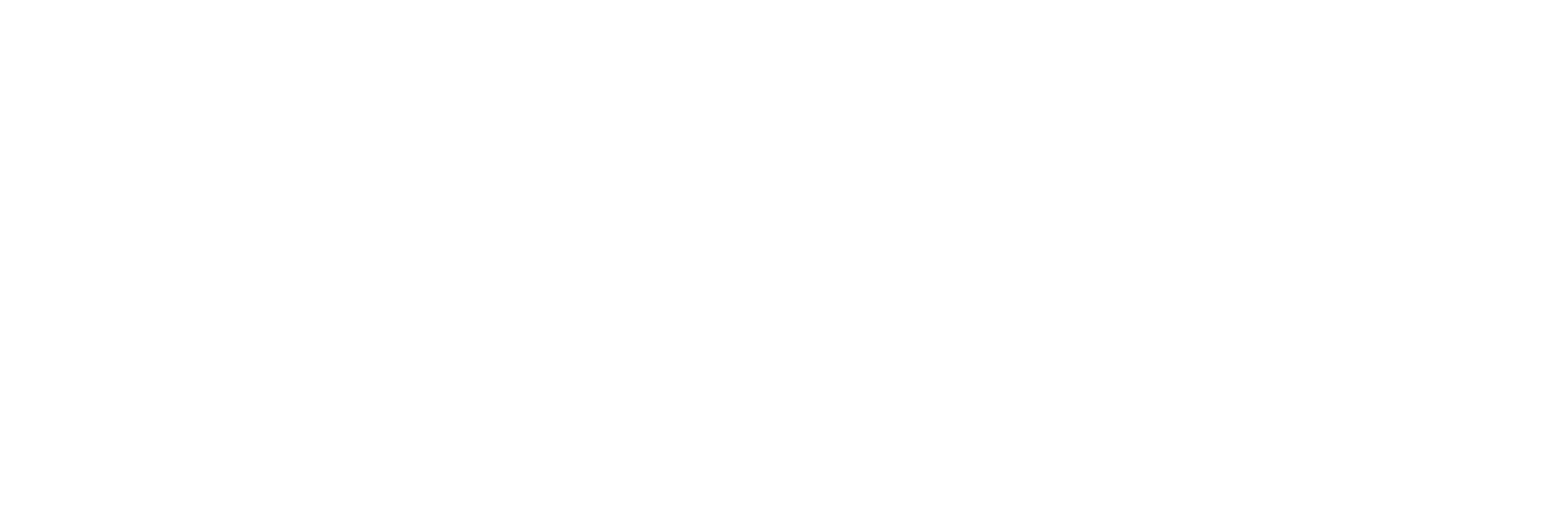『お祈りの場所』
「お祈りの場所を決めよう」とユノムは遠くを見つめながら言った。
脈絡は一切ない。公園のベンチに座ってサンドウィッチを食べていたはずなのにどうしてそんな話題が始まるのかと私は驚く。
「お祈りの場所?何を祈るの?」と私が聞くとユノムは振り返りもせずに笑った。最初はクスクスと、そして、こっちが思わずあっけにとられるくらいに長い間笑い続け、最後には腹を抱えてゲラゲラと笑った。
私は、ユノムらしいな、と思った。昔からこの人はそうだ、箸が転がっただけでおかしい年頃、という表現があるけれど、ユノムの場合はその年頃がいつまでも続いている様子で、なんでもないことで笑い出すことが多かった。こちらとしては何がそんなにおかしいのか全く理解ができないのだが、ついついユノムに合わせてヘラヘラと中途半端に愛想笑いをするのが常だった。なんで笑うのかもわからないのに笑っている私は、なんだか自分がチグハグな気がしていやな気持ちになる。だけれど、これはユノムのためなのだ、と決め込んで、愛想笑いをする。そんな時に限って、ユノムは突然ピタリと笑うのをやめる。振り回されたこっちは、愛想笑いの時間が終わったことに安堵しながらも、それなりに苛立つ想いも抱く。
笑いやめたユノムは突然に真剣な顔をして話し始めた。こっちも、真剣に聞くふりをする。そんなふりをしたところでユノムはこっちを見てはいない。ユノムは話すときに私のことを見たりしないのだ。
「お祈りってさ、しなくない?普段。え、マル、してる?寝る前とか、あー、やばい、って時とか、お祈りしてる?」
ちらりと目を向けられて、私は首を横に振る。私は無宗教だし、オカルトの類はどちらかといえば嫌いだ。あ、マルってのは私の名前。
「でしょ?あたしもしないわけよ、お祈り。何に祈ればいいんだよ?って感じだしさ、神様なんていないと思ってるしさ。だって、ね、神様の恩恵に預かったー、て思うこと、日頃一切ないもんね。いないいない、多分、いない、神様。いるんだとしたら、神様サボりすぎだろ、って思うわけよ。神様いるなら地震とか起こしてんじゃねえよ、って思うし、地震起こすことも神様の思し召しだっていうんだったら、あたしそんなサイコな神様には祈らないわ。むしろ距離おくわ。積極的に逃げ出すわ。」
「そうだよね、私も、神様とかちょっとわからないかな。」
「見てよあれ」
ユノムが顎で示した方に目をやると、ボロをまとったホームレスが空き缶を拾っていた。詳しいことはわからないが、ああやって集めた缶を鉄くず屋に売るのだろう。
「貧富の差ってやつだよ。ひどいよね、諭吉何枚もはたいて高級ディナー食べる奴がいるこの街の公園にさ、空き缶拾って生計立ててるおっさん住んでるんだよ?あのおっさんの今夜の晩飯なんだろね、コッペパンだよきっと、コンビニのやっすいコッペパン。あんことマーガリンの。あ、レストランの裏口に行って残飯とかもらうのかもね。ひゃあ、悲惨!そう思うべ??」
私はユノムに相槌を打つことにすごく後ろめたさを感じた。ホームレスを見すぼらしく哀れだと思うことは、とても罪深いことのように感じた。けれど、あれが自分だったらと思うとゾッとした。
「優しく立派な神様がいるんだとしたら、なんであんな生活してるおっさんが世の中にいなくちゃいけないんだ、って思うわけよ。不平等過ぎだろって。これでさ、金稼いで欲まみれのふざけた人生送ってるやつにバチでも当たるんだったらいいんだけどさ、実際、そんなことないもんね。不幸そうな奴が不幸なまま死んで、幸せに豪遊している奴はある程度幸せに死んでいくんだ、きっと、おおむね、高い確率でそうなんだ。」
確かにそうだな、と私は思った。
「マル、あのおっさんのことジロジロ見て哀れに思うの、なんか後ろめたいな、って思ってるでしょ?」
私はギクリとした。
「ほら、目をそらさない。しげしげと見つめて。で、想像してごらん。あのおっさんが最期の最期、どんな死に方するのか。どうかね?寒い日にアスファルトの上で凍え死んでるかね。交通事故かね。ある日倒れてるのを発見されて病院に運ばれるも、家族に連絡する手段もなく、大した治療もできず・・・」
「やめよう。もう行こう・・・」
立ち上がろうとする私の腕をユノムが掴む。私はベンチの上に尻餅をつく。ユノムは私の顔を両手で挟んで、ホームレスの方を無理やり向かせた。
「やめてよ!」
私はユノムの手を振りほどいた。思わず大きい声がでた。実際私は、ホームレスの最期をあれこれと想像し始めてしまっていた。どうしてこれまで、想像したことがなかったんだろう。ユノムはベンチに深く座り直し、背もたれに体重を預けるとぼんやりと遠くを見つめた。怒らせてしまったかと思ったけれど、むしろ笑っていた。
「マル、なんで後ろめたいと思うんだと思う?」
「は?」
「それってさ、多分だけど、神様に心のなか見張られてる気がしてるんだよ。」
「神様に?」
「だって、あんたがどんなに縁起でもないことを想像したとしても、上から目線でおっさんのこと蔑んだとしても、偽善者よろしくおっさん哀れんだとしても、そんなの周りには気付かれないし、実際にはあんたがなんか思ったくらいで世界は変わらない。普通に考えてそうなのに、あのさ、ぶっちゃけあたしもだわ。心の中にうっかり汚い気持ちを抱こうとすると、あ、これやばいぞ、バチ当たるぞ、みたいな気持ちになるわけ。神様なんか信じてないのに、なんか、誰かに心の中のことバレて、怒られるぞ、みたいな気持ちになるわけ。」
「・・・ユノムは、神様がいないって思ってるんでしょ?」
「いないと思ってる。でも、いたらヤバいなって気持ちにもなってる。だからさ、マル、お祈りの場所、決めよう。」
「どういう意味?」
「祈るのよ毎日、毎日祈るの。ま、毎日は無理かもだけどさ、決まった場所でいっつも、神様に祈るの。例えば・・・貧富の差を無くしてください、とか、災害が起きて悲しむ人がいなくなりますように、とか。で、あたしは超絶真面目に生きる。もう、ね、神様が喜びそうな生き方しまくるわ。毎日祈って、清楚な生き方するわ。募金とかするしさ、嘘もつかないし、もう、男友達と二人で飲みに行ったりもしない。まあ、神様の性格わからないから、何が神様に喜ばれるのか傾向と対策が微妙ではあるんだけどさ、思いつく限り神様好みの生き方するわ。だってさ、思うんだよね。祈り方間違ってたくらいで祈りを聞き入れないほど器小さくないでしょ、神様。子供がお小遣い必死で貯めて誕生日プレゼント買ってきたらさ、それがなんであったって喜んで抱きしめてやるのが親ってもんでしょ?」
ユノムの理論はよくわからないけど、わかるような気もする。
「つまり、ユノムは神様に世界を素敵にしてくれるように一生懸命お祈りして、その願いを聞き入れてほしいってこと?」
「違う。聞き入れないでほしい」
「ほぇ?」
変な声がでた。ああ、だめだ。わからない。いつものことだけれど、ユノムが何を考えているのかついていけない。
「あたしが命がけで超絶祈り続けてさ、それでもその願いが聞き入れられなかったら、あれじゃん、いよいよ証明できるじゃん。」
「証明?」
「神様なんていないんだって証明。少なくとも、あたしを幸せにしてくれるような神様はいない。もしくは、あたしは神様から嫌われている、って、納得できる。未練がなくなるじゃん。もう、嫌なんだ。なんかするたびに心のどこかで、神様に後ろめたいぞ、みたいな気持ちになるの。自分が今あんまりイケてる人生じゃないのは、何かしら神様に恥ずべき人生だからだ、とか思っちゃうの。でもさ、本当に、いるならね、超かっこいい、すげー慈悲深い神様がどっかにいるならさ、その人には愛されたいわけよ。悲しませたくもないわけよ。でもさ、もし神様がいないならさ、年がら年中その人のために生きてくの超アホじゃん。ああ、こんなことしたらあの人に悪いな、とか思うの、損じゃん!だからね、祈るよ、あたしゃ。祈って祈って、ちゃんと願いを聞き入れないでもらったら、晴れてあたしゃフリーってわけさ!さ。決めるよ。祈る場所。」
ユノムは立ち上がって歩き始めた。私の方を振り返ったりしない。でも、置いてけぼりにしようとしてるんじゃないってことはわかってる。自分が歩き始めれば、私が当たり前についてくると思ってるのだ。私は苛立ったような気持ちを抱きつつ、置いてかれないように急いでユノムを追いかける。ユノムは笑ってる。なんでこのタイミングで笑うのかはわからないけど、私も、合わせて笑う。なんで笑うのかもわからないのに笑っている私は、なんだか自分がチグハグな気がしていやな気持ちになる。だけれど、これはユノムのためなのだ、と決め込んで、笑う。
ユノムのために笑い続けて、笑い続けて、それでもユノムがこっちを振り返ってくれないんだってことがいつか証明できたら、そしたら私は晴れてフリー、ユノムのいない人生を存分に謳歌してみせるんだ。ユノム、どうかどうか振り返らないでね。私はいつものように祈りながら、笑う。ユノムのことを、追いかけながら。