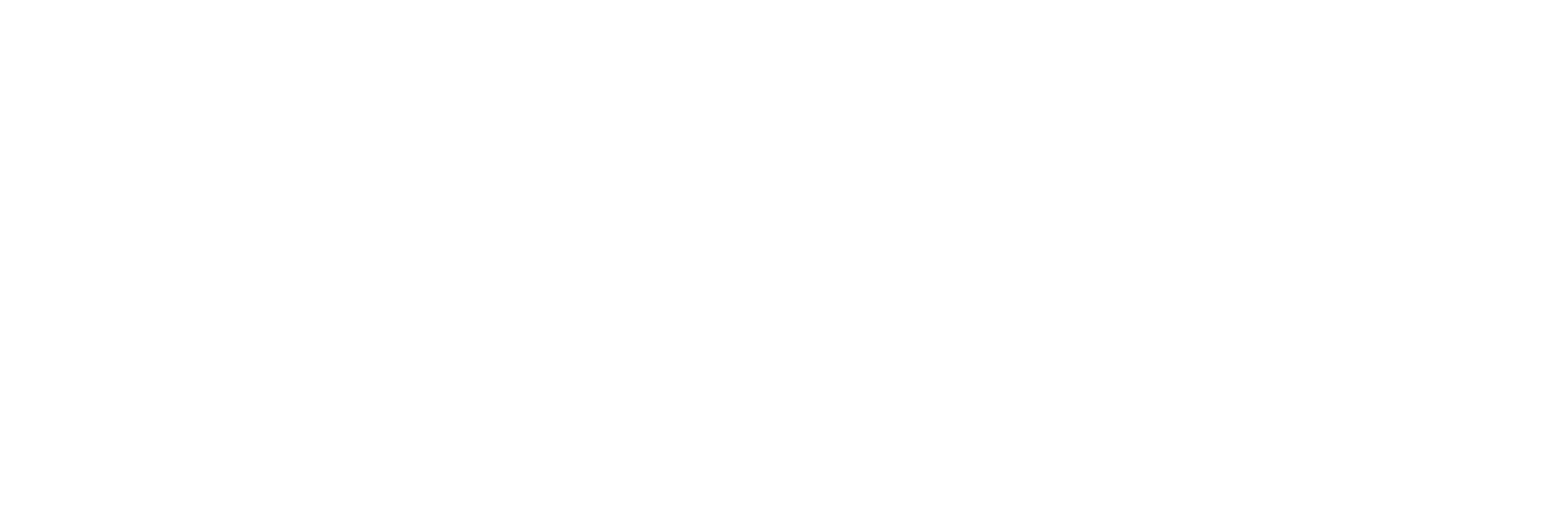『 鏡の前で自殺をした少年について』
少年は鏡の前で自殺した。
部屋には血の匂いが立ち込めたし、絨毯は真っ赤に染まったが、彼の両親だった男女は少年の亡骸には目もくれず、鏡を見つめて笑っていた。それからどれほどの時間が経ったのかもわからないし、その鏡が今現在どこにあるのかも定かではない。人知れず行われたことなのでこのまま誰にも知られなくとも構うまいが、人知れぬ物語をこっそり打ち明けるのも色気のある行為だと思い立ち、ここに、この物語についてとどめておく。少年はなぜ鏡の前で自らの命を絶ったのか、もしもあなたが今とてつもなく暇なのであれば、ご一読いただくといい。
子供が大人になるのは、子供時代に飽きるからである。
自らの子供時代というものが周りから愛されている自覚はあるものの、当の本人はとっくにそんなものには飽きてしまって、これが永遠に続くのであればもう死んでしまうか、もしくは子供以外の何かになってみようと考えるのである。しかし、周りがそれを許さない。
宮崎ルイの場合もそうであった。ルイはもう幾ばくものあいだ、いかにも子供らしく子供であり続けた。子供であることを全うするために様々な文献を読み漁り、練習などもした。ふとした瞬間にアドリブ的に放った子供らしい発言が周りを盛り上げたことがあれば、後からそれを事細かに思い出し、きっちりと手帳に書き込んだ。どのような状況で、どのような塩梅で、どのような行為、発言をしたか、それにより周りはいかにルイのことを子供扱いし、歓喜したか。手帳の中には今や子供が子供であるためのメソッドが体系立てられてびっしりと書き込まれていた。もちろん、手帳とはいえどもそれは「自由帳」と呼ばれる、表紙に大きく昆虫の写真が載っているものである。
「さすがに、飽きてしまったな。」
ルイはある朝、唐突に確信した。いや、予感はあった。積み重なる違和感はルイの体の中で年々膨らみ続け、ついには破裂してルイのことを殺してしまいそうにまでなっていた。ルイは母親に愛されていた。父親にも愛されていた。かつては近隣の住人にも愛され、両親は自慢げにルイを見せびらかして外を歩いたものだ。しかし、それもかつてのこと。今ではルイは家の外に出ることはない。
「もう、僕はどれだけの時間、子供であり続けたのだろう」
ルイは記憶を丹念に探って懸命に思い出そうとしたが、それは失敗に終わった。恐らくは、彼の両親でさえも思い出せぬことだろう。実のところルイは、もう半世紀以上もの間、子供のままでい続けていた。
遠い昔に同級生であった者たちはとうの昔に中年になり、誰かの親、もしくは祖父母にまでなっていた。しかし、ルイは、未だに子供のままだったのである。大人になる宣言も決意もないままにひたすら子供であり続けようとしてきたルイの姿形はいつまでも子供のまま、いやむしろ、年々、子供らしさは輝きを増しているようにさえ思えた。
「僕はおそらくは世界でいちばん熟練した子供だろうな。普通のみんながせいぜい数年間で子供をやめてしまうところを、僕の場合はそうではないのだもの。何年も何十年も逃げやしないで子供であり続けたのさ。でも、あぁ。飽きちゃった。飽きたということを自覚してしまったら、もうこれ以上は耐えきれないや。今夜夕食の時に、パパとママに話そっと。」
夕どき、「ご飯よー」と台所から声がするとルイは子供部屋から出て行った。父親はさほど広くはないテーブルの席に着き、すでにビールを飲んでいた。母親はエプロン姿でキッチンに立って、笑顔でルイのことを迎えた。夕食の献立はオムライスだった。黄色いふわふわの卵の上にはケチャップで可愛らしい顔が描かれている。
「わーお!オムライスだ!」
「ほらほら、ちゃんと手を洗ってからにしなさい!」
母親はわざと芝居がかった調子で、スプーンを握ったルイの手をペシリとたたいた。「ちぇー」とルイはこれまたひょうきんな顔をして見せ、洗面所に向かった。
「まったくルイのやつは本当に落ち着きがないな。ルイ!そろそろお兄ちゃんなんだから、ちゃんとしないとみんなに笑われるぞ」顔を赤らめながら笑う父親はいつものように上機嫌だった。手を洗い終えたルイは「そのことなんだけどね・・・」と言いながら席について、話した。
「僕さ、そろそろ子供でいることをやめてみようかと思うんだ。」
母親が運んでいたスープ皿を床に落とした。それからしばしのあいだ、冷たい沈黙が食卓を支配した。やがて父と母は息子にいくつかの質問を投げかけ、息子はそのすべてに丁寧に答えた。息子は両親のことを心底愛していたのである。しかし、やがて父親は激昂した。目には涙を浮かべて、大きな声で聞くに耐えないような罵詈雑言をルイにぶつけ、顔は先ほどとは比べようがないほどに真っ赤であった。猛り狂う父親のことを母親が止めた。それでもなお、父親は声を荒げた。
「ルイ、大人になることだけは許さない。そんなのは、子供がすることじゃない!」
父親がこんな顔をしたのは初めてだった。ルイは子供らしく泣きじゃくりながら必死に叫んだ。
「でもね、僕はどうにもこれ以上は耐えられそうにないんだ。もし大人になることを許してもらえないのだったら、あのね、僕は死んでしまおうと思うの。」
母親は涙を流しながらルイのことを抱きしめ、そして言った。
「そう、そうよね。ルイは、そういう気持ちなのね。だけどママはね、ルイが大人になるなんて嫌なのよ。子供のルイが大好きなの。だから、残念だけど、死んでしまいましょうね。」
こうしてルイは自ら命を絶つことになった。
父親の勧めによって、工作用のカッターナイフを用いて喉元の頚動脈を切ってしまうことになった。なんの変哲も無いただの自殺だが、一風変わっていたことがあったとすれば、ルイがその自殺を鏡の前ですることになった点だ。
ルイの両親はとある密教に入信していた。教義によると、鏡の前に立ち鏡を見つめながらに命を経てば、現実の命が途絶えた後でも人は鏡の中で生き続けるというのだ。じっさい、その密教の総本山と呼ばれる場所にある蔵の中にはおびただしい数の鏡が収められていて、その鏡の前には誰も立っていないというのに、中には人が映っている。そして、言葉を交すことこそできないまでも、いつまでも変わらぬ姿のまま、目をパチクリさせたり、口をばくばくさせたりするというのである。
その晩、最後の食事を終えたルイは、両親に見守られながら鏡の前に立ち、小さなカッターナイフを持った。
「パパ、頸動脈ってこの辺りでいいんだよね?」
「さすがはルイだ、前に買ってやった図鑑に載っていたのをしっかり読んだんだな。」
ルイは鏡の中の自分と見つめ合い、カッターナイフを首のあたりに当てがうと、力を込めて一気に振り抜いた。ルイの首からは鮮血が溢れ、ルイは崩れ落ちた。あたりの絨毯は瞬く間に赤く染まった。
両親は鏡の方を見つめ続けていた。そして、優しくにこりと笑った。鏡の中にはつい数秒前と同じ姿のまま、ルイがこちらの方を見つめていた。首にあてがったカッターナイフをゆっくりと下ろすと、鏡の中のルイはにこりと笑った。母親は優しい声で言った。
「さ、ルイ。夜も遅いのだから、休む準備をしましょうね。」