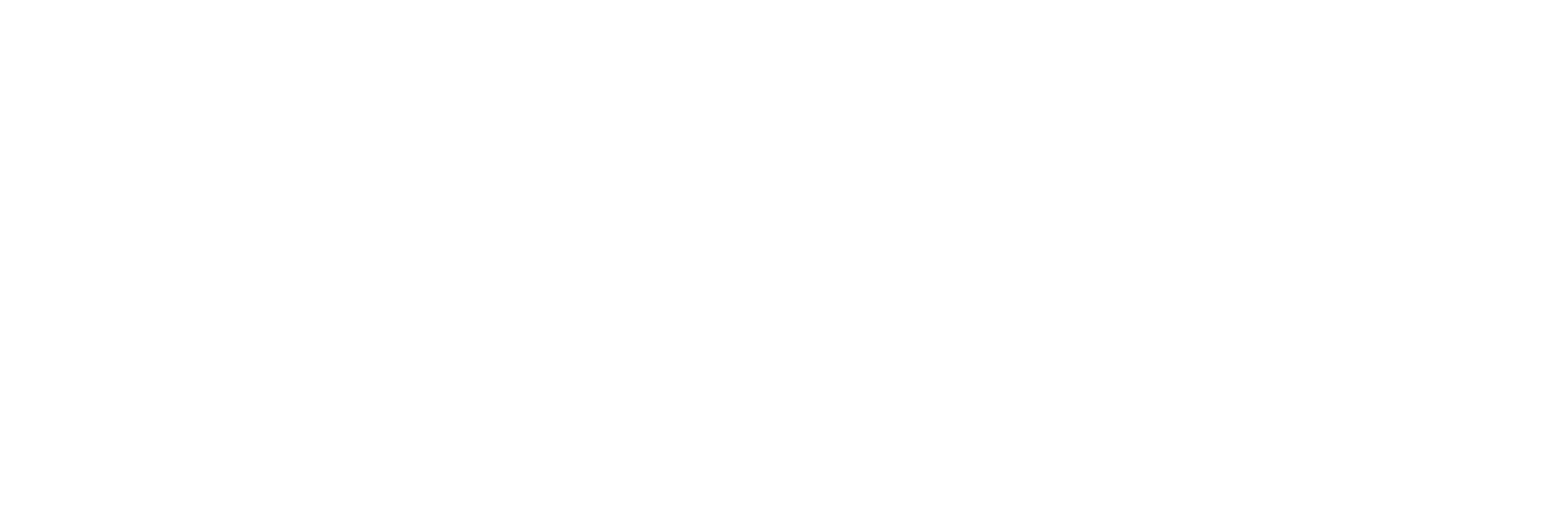待ち合わせをしているのは間違いなかった。ただし、モルは自らが仕出かした重大なミスに気づいてはいた。待ち合わせの場所と時間を、ララに伝え忘れていたのだ。いや、待ち合わせをしようという約束すら伝えたかどうかが曖昧だ。伝えたはずだ・・・いや、どうだっただろうか。
リス園の網が破れたのは突然で偶然のことだ。
月の大きな夜のこと、近隣を歩いていた酔っ払いが、何か癪に触ることでもあったのだろう、あたりに捨て置いてあった金属バットを振り回して金網を破ってしまった。金網というやつは何せリスを閉じ込めるためのものだ、そう簡単に破れないくらいには強く作られていたはずだが、しょせんはリスを閉じ込めるくらいのものだ、人間様が思い切り暴力をふるったら簡単に破れてしまったことくらいは許してやってほしい。
なんにせよ、リスたちは突然に外界への扉が解き放たれることになって、驚いてしまった。
・・・・・・・・・・・
園の中に何百匹と閉じ込められたリス達の中には、外界に夢を馳せる者もいれば、外の世界など想像すらしてはいない者、何があろうともリス園の中からは出たくない者、などなど、様々な者達がいた。
モルに関しては、そのことについてはどうでもよかった。
なぜならモルには友人がいたからである。園の中であろうが外であろうが、モルは自分の居場所はララの隣だと思っていた。これはとても単純で便利な考えで、小さなリスの身からしてみたら、とてつもなく身分相応、身の丈にあった、素晴らしい自分の座標認識であった。モルは方向感覚に関しては決して明るい方でなかったので、せいぜいが数エーカーほどしかないリス園の中でさえよく迷子になったものだが、それでも彼は慌てはしなかった。どんな時でも、ララとの位置関係で自らの位置を認識していたからだ。ララというのは・・・モルの親友であるリスのことである。
ララとなぜ仲良くなったのかはわからないし、いつ仲良くなったのかもモルは覚えていなかった。モルはそのことを残念だと思うと同時に、とても誇らしく思っていた。理由やきっかけが曖昧なのにも関わらずかけがえのない親友としてそばにいる自分たちは、何か超常的な力で結び付けられているような気がしたからだ。きっとこれからどんな理由で離れ離れになったとしても、きっと自分たちは再び出会えるだろう。神や仏という概念はリス風情のモルは当然知らなかったが、何か運命的な力が自分たちをきっと永遠にそばに居させるだろうと信じて居た。
ララは、外の世界についての強い興味を抱いていた。
「なあモル、僕たちはこれから先、然るべき時にはきっと、もっと彩りのある生き方をし始めるべきだ。モル、想像してごらんよ、とてつもなく幸せなはずだよ。僕たちは出て行くんだ、今のこの鉄条網に隔てられた小さな世界から外に出て行くべきなんだよ。」
ララはいつだってモルにそう語って聞かせ、モルはそれを聞くたびにうっとりとした。外の世界のことを想像するだなんて頭の悪いモルには難しいことではあったけれど、ララが満面の笑みで語るその夢は、きっと素敵なことに違いないと思った。
「モル、見上げてごらんよ。ほら、お月さん。とっても大きくて綺麗なのに、このリス園では天井にまで忌々しい鉄の網が覆いめぐらしてある。おかげで、別嬪なお月さんが台無しさ。ここから出ればさ、お月さん、もっともっと綺麗に見えるはずだよ。僕らそれを、一緒に見上げるんだ。きっと、泣くほど最高な情景さ。それに、何処へだって行ける。川だってあるだろうし、山に行けば、ここで人間が用意する餌では到底お目にかかれないような木の実にだってありつけるだろう。自由なんだ。今ここでの生活では考えられないような感情を、きっとたくさん知ることができるだろうさ!」
モルはたまらなく嬉しくなってしまって、ララの肩をガッと力強く掴んで自分の方を向かせる。
「何?どうしたんだよ、モル。」
しかし、ララにまっすぐ見つめ返されると、モルはいつだって黙ってしまう。本当は、言いたいことがあったはずなのにだ。
「まあ、でも、モル、僕は随分と大それた夢を見ているのかもしれないね。リス園の外に出ることができたとしたって、それはきっと大変なことさ。道しるべもなかろうし、ここと違って食べ物だって自分で調達しなければならない。嵐の闇夜には凍えるだろうし、野良犬だとか野良猫だとか恐ろしい獣の餌食になってしまうことだって覚悟しなくてはならないかもね」
「そうだね。きっと、そう言うことも、覚悟しなくてはいけなかろうね」
「なあ、モル。いつか、僕と一緒にリス園の外に出たいだろう?」
「・・・・・・」
どうして返事ができないのか、モル自身もわからなかった。モルの居場所はララの隣だとモル自身決めていたし、ララと離れ離れになることなど想像だにしえない。さらには、ララの語るリス園の外・・・鉄条網に隔てられないでみることができる大きな月だとか、食べたことのない木の実だとか、自由のことだとかを考えれば心が浮き立つ。
「ああ、ララ、鉄条網の向こうに一緒に行くと約束するよ!」と叫びたいのだが、なぜだろう。モルは、自分でも不思議なことに、いつもそれを言いそびれるのだった。だけどモルは、精一杯にララに伝える。
「ララ、ずっと一緒にいようね。もしも離れ離れになることがあっても、僕ら絶対に待ち合わせをして、再会するんだ。」
モルがララを抱きしめると、ララはニコリと笑って、「もちろんさ!」といたずらそうに笑い返してくれるのだった。
・・・・・・・・・・・・
そして、ある月の大きな宵のこと・・・
その晩はとりわけ寒い夜だったもので、モルとララは木のうろの中の暗がりで身を寄せ合って眠っていた。突然にガシーンガシーンと言う大きな音が聞こえたものだから外を見てみると、酔っ払いがダミ声で叫びながら鉄条網に向かって鉄バットを振るっているではないか。モルとララは怯えてしばらく身を隠して様子を伺っていた。しばらくして、突如、リス園中にウーーーウーーーーーとけたたましい警報音が鳴り響いた。うろから顔を出して外を見ると、そこかしこに設置された赤い点滅ランプが夜を真っ赤に染め上げた。おそらくは防犯用にそのようなシステムが組まれていたのだろう。酔っ払いは大慌てでバットを放りだして、どこかへ逃げ去ってしまった。
「ララ!驚きだね!まさか僕たちのリス園がこんなにハイテクノロジーな方法で管理されていたとはね!僕らが思うよりも僕らは大切に扱われていたのかもしれないよ!」
冗談めかして笑うモルに、ララが鋭く声をあげた。
「モル!見てごらんあそこ!鉄条網が、破れてる!」
モルがララの指差す方に目をやると、なるほど、どうやら、さっきの酔っ払いの仕業らしい、張り巡らされた鉄条網のほんの一部が地面まで避けている。大きな割れ目とも言えまいが、リスぐらい通るのには差し支えなどありようもない。
「モル、行こう!」
ララは叫ぶと、すごい勢いで木を降りた。
「ララ、ちょっと待ってよ!」
出遅れたモルは木の上から叫んだ。
「何してるんだ?早く!外に出るチャンスだよ!ほら、みんなも騒ぎ出した・・・!」
見ると、おびただし数のリス達が、鉄条網の裂け目に向かって一斉に走り出していた。
「モル!行こう!早く!」
「・・・・・・」
「警報がなっているんだ、早くしないと人間がこっちに来てしまうよ!さあ、降りて来て!」
モルは慌てて木から地面へと降り立った。
「モル、行くよ!ついて来て!」
ララはすごい勢いで走り始めた。モルは必死にララを追いかけた。途中でたくさんのリス達の流れに飲み込まれ、ララを見失ってしまった。追いかけなくちゃ、急いで追いかけなくちゃとモルは思ったが、モルはついうっかり転んでしまい、その瞬間にララを見失ってしまった。モルは必死に立ち上がろうとしたが、できなかった。膝が震えて、腰が抜けていたのだ。なぜだ、なぜだろう。リス園の外に出る、そうして、ララと一緒に広い世界で暮らすんだ。その様を想像して何度も何度も自分を立ち上がらせようとするものの、どういうわけか、モルの体は震えるばかりだった。あたりは、おびただしい数のリス達の足音や叫び声で耳を塞ぎたくなるほどの喧騒に包まれている。土埃が立ち込める中、モルはうずくまるしかなかった。
モルがついて来ていないことに気がついたのだろうか、前の方から、喧騒に紛れてララの声が聞こえた気がした。
「モル!どこだ!どこにいる!早く!急ぐんだ!!一緒にいかないのか!?」
もちろん、ついて行くつもりだった。でも、モルは立ち上がることができず、声が出なかったのだ。
「どうしたんだ!返事をしてくれ!どこだ、どこにいるんだ!先に行ったのか?外で待っているのか!?」
たくさんのリス達のせいか、暗がりのせいか、ララがどこにいるのかがわからない。
遠くから、人間達が懐中電灯で辺りを照らしながらやって来た。
気付いたリス達はより一層に勢いを増して、外に向かって走り始めた。人間達も大騒ぎをしている。大変だ、早くしないと。ララはまだ見つからなかったが、モルは震える体を引きずり、どうにか鉄条網の破れたところから外に出た。リス園の外へとでた他のリス達は人間に見つかるまいと、少しでも遠くへ逃げるべく外の世界の闇夜に向かって走り去っていった。しかし、モルにはできない。モルは泣きそうな気持ちで、近くにあった岩の陰に身を隠した。心臓がバクバクと鳴って破れてしまいそうだった。駆けつけた人間達は何やら大声をあげて、あっという間に、鉄条網の破れた部分を直してしまった。あまりの恐ろしさに、モルは目を閉じて人間達が立ち去るのを待っていた。
あたりが静かになって、モルが恐る恐る目を開けてみると、そこには誰もいなかった。
モルは小さな声で「ララ・・・?」と呟いてみたけれど返事はない。見渡したところで、近くにいる様子もなかった。
空を見上げると、大きな月が昇っていた。
鉄条網越しではない月はあまりに美しかった。
モルは、悲しくて仕方がなかった。
ララのところへ行かねばならない。待ち合わせをしているのは間違いなかった。ただし、モルは自らが仕出かした重大なミスに気づいてはいた。待ち合わせの場所と時間を、ララに伝え忘れていたのだ。いや、待ち合わせをしようという約束すら伝えたかどうかが曖昧だ。伝えたはずだ・・・いや、どうだっただろうか。
モルは歩き始めた。どこへ行けばいいのかはわからない。けれど、今いるその場所が自分に居場所ではないことは間違いなかった。モルの居場所は、ララの隣。モルはいつからだったかずっとずっと先だってから、そう決めていたのだから。歩きながらモルは、独りでいるのにも関わらず、喋り始めた。
「・・・君の随分と大それた夢について、実のところ、僕もいつだって考えていたのだよ。考えていたというのに、口達者な僕がそのことについて何も言わなかったのはとても不思議なことさ。でも、大切なことだからね、本当に大切な言い方でしか、そのことについての言葉を話したくなかったんだと思う。」
とぼとぼ。とぼとぼ。ララを探して歩いた。あてずっぽうだけれど、確信はある。出会えないわけなどあるわけもない。
「・・・ねえ、ララ。君と、リス園の外で生きていきたい。」
モルはちらりと、リス園を振り返ってみた。今までなんの不満もなかった場所だったけれど、こうしてみると、とても狭苦しい場所に思えた。
「・・・しかし、大変なのはこれからさ。道しるべもなかろうし、食べ物だって自分で調達しなければならない。嵐の闇夜に凍えぬように注意しよう。野良犬だとか野良猫だとか恐ろしい獣の餌食になってしまうことだって覚悟しなくてはならないかもね。君、とりあえず逃げたものの、きっと途方に暮れているのだろう。」
とぼとぼ。とぼとぼ。
「大丈夫、今、迎えにいくよ、僕が君の元へ駆けつける。きっと行くから待っていておくれね。恐ろしくなったらちゃんと僕に伝えたまえよ。僕はちゃんと、手を貸すからね。外の世界は恐ろしいね。でも大丈夫だよ、僕はきっと、君のところに行くからね。」
とぼとぼ。とぼとぼ。
風が吹く。ただただ、風が吹く。
小さな小さなリス何匹だろか。
それぞれの思いを抱きながら、大きな世界を、とぼとぼ歩く。