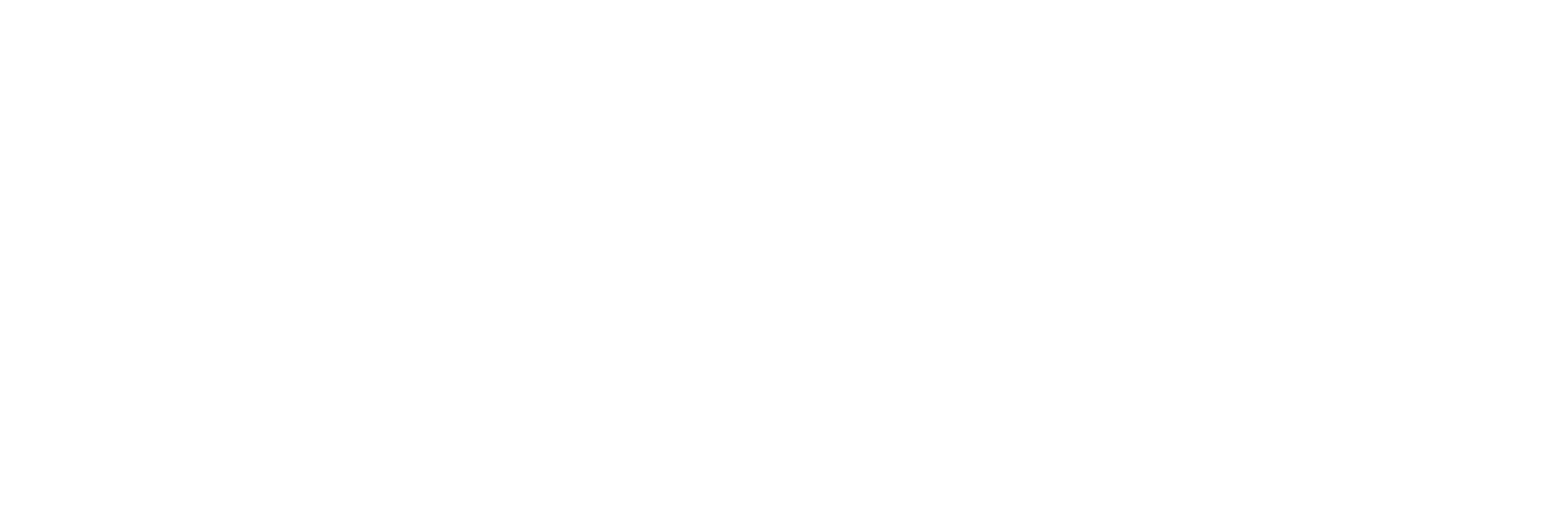筋野一徹は年金暮らしをしていた。古いあばら屋で、振り込まれる月に数万円の金銭を切り崩しながらひっそりと暮らしていた。妻子はいない。孤独であったが、それでいいと若い頃に決めたのは自分だ。一徹には幼い頃からの夢があった。
日本一のラーメンを作る。
寝ても覚めても一徹を狂わせ続けた夢だった。高校卒業後すぐに一徹は、これはと思ったラーメン屋に弟子入り修行し、朝から晩までラーメンを学んだ。少しでも評判のいいラーメン屋の噂を耳にすれば、時間と金には糸目をつけずどんな場所へも出かけた。80歳になるまでに、18人の師匠に従事した。様々なラーメン屋で若手のアルバイトに混ざって働き続けながらも、「自分はまだ修行中の身ですから」と言っては誰よりも早く店を訪れて掃除し、安月給で働くことを甘んじて受け入れた。定年退職をやり過ごし75歳までは店に出ていたが、ここ数年は体力も衰えたため師匠からは離れ、自宅でのラーメン研究に没頭していた。
80歳の誕生日になると、一徹はこれまでに従事した全ての師匠たちに手紙を書いた。
「敬愛なる我が恩師へ。
この世の全ては因果応報、身に起きる悪しきことは全てが身から出た錆と存じておりますが、この度、病を患いました。他人に迷惑をかけ続け生きてきたことは百も承知なため、右往左往するつもりはありません。ですが、余命が幾ばくかもわからぬとなった折、大変に罪深きことではありますが私はどうしても、今こそ自分自身のラーメンを作ってみたいなどと考えるに至りました。無論、まだまだ修行の身、恐れ多いことだと自分を律する思いがあるのですが、死を目前に控えたいま、どうにも幼き頃からの夢捨てきれず情けないばかりです。老いぼれの最期のわがまま、冥土の土産欲しさの戯言と思い、どうか未熟な私めがラーメンを作るお許しを、いただけないでしょうか。」
要するに、自分のラーメンを作る許可を頂きたいと申し出たのである。18人の師匠のうち、ただのひとりでも許してもらえなければ、一徹は諦めるつもりであった。しかしこれは土台、間の抜けたな話で、そもそもがラーメンを作るのに許可など必要あるはずもない。何よりも、一徹こそは修行だと思っていたものの、全ての「師匠」たちは、彼をただの熱心なアルバイトだと思っていたのである。一徹の緊張感など素知らぬ様子で、18人全てが一徹にラーメン作りの許可とエール、それと、体を見舞う文言を記した返事をよこした。中には、かつて共に働いていたアルバイト店員たちの寄せ書きや、写真が同封されているものもあった。
一徹は歓喜した。ついにだ。ついに来たのだ。自分のラーメン。自分だけの、日本で一番のラーメン創りに挑戦するのだ。
一徹は患って動きの不自由になった体を奮い立たせ、ラーメン創りを始めた。長年の修行の成果とばかり、昆布、魚、豚、牛、鳥・・・はたまた世界各国の様々な出汁という出汁を掛け合わせ、他のどこにもない、一徹自身のスープを完成させた。麺の打ち方にも命を注いだ。小麦粉のみならず餅粉、タピオカ粉、そば粉を絶妙な分量で混ぜ合わせ、南米のステサムラと言う香料を少し混ぜるのが一徹の行き着いた最高の麺のレシピだった。かん水の性質も熟知していて、味、歯ごたえ、香り共に申し分のない出来だった。もちろん、スープと麺が喧嘩し合っては何もかもが台無しなのだが、一徹のコンダクターとしての実力は素晴らしく、スープと麺は相性抜群のハーモニーを奏でていた。不眠不休で挑んだことが見事に成果をだし、一年とかからずして、一徹は一徹にしか創れない、一徹自身のラーメンを完成させた。それが日本一であったかどうかなど、そもそも基準もないことだが、それは間違いなく、一徹には納得のいく出来栄えだった。
一徹は大急ぎで師匠達に連絡をし、自分のラーメンの試食会をするので訪れて欲しいと願った。師匠達はそれぞれの店を回すことで忙しかったのだが、何せ、死にかけの老人からの頼み事である、無碍にもできない。誰もが、一徹のラーメンにかける熱意の凄まじさを知っていたし、それぞれが自身の中にもそう言った熱意ーー狂気にも似た愛ーーについては心当たりがあったので、スケジュールの調整をして一徹の元を訪れることにした。
試食会が行われたのは一徹の住む薄汚いあばら屋でのことである。農作をやめてしまった片田舎の広大な畑が何にも使われぬまま土地として空いていたので、そこに一徹は住まわしてもらっていたのである。広い広い荒れ果てた畑の中にポツンと立っているあばら家はそれはそれはみすぼらしかった。生まれてこのかたラーメン屋でのアルバイトしかしてこなかった一徹である。女にも酒にも博打にも目をくれず、遊ぶことなくひたすらラーメンに人生を捧げてきたが、そもそもが安い賃金での労働であったし、金があればみな、ラーメン研究のための旅費や、ラーメンに関する書籍を買うのに費やしてしまった。ましてや一徹は誰彼構わずラーメンをご馳走することが大好きだったものだから、一徹は恐ろしいほどに貧乏だった。「誰彼構わず」というのは本当のことで・・・例えば、バス停で一緒に並んでいた人や、夜の街でへべれけになっている酔っ払い、塾の帰りに腹をすかせた中高生、はたまた、一徹が住んだことのある街のホームレスで、一徹にラーメンを奢られたことのない者などいるはずもなかった。
貧乏な一徹は汚いあばら屋で、貯金を切り崩してラーメン創りに励んだのである。今では毎月振り込まれる些細な年金だけが頼りであったが、食材にはいくらでも金をかけた。全国津々浦々から訪れた一徹の師匠達はそのあばら屋の今にも崩れて埋まってしまいそうな佇まいに驚きを禁じ得なかったが、漂う香りが彼らの鼻にたどり着くや否や、目の色を変えた。思えば集ったのはものすごい面々である。それぞれが伝説と仰がれる日本ラーメン界の王者、神々である。互いが互いのことを知っていたが、壮絶なるライバル関係でもある。一徹の存在がなければ一堂に会することなど有りえぬ者達であった。その王者達が、あばら屋に漂う香りに反応した。
「一徹、貴様・・・」
北九州で最も隆盛を誇るラーメン屋「粉詩坦々」の店長、錦戸龍が一徹のことを睨んだ。一徹よりは年下だが、天才と呼ばれるひとりである。
「一徹さん、やりましたね。いや、やられました、というのが正しいかしら。」
北海道ラーメン「愛のキムンカムイ」の女店長、艶やかなる女王として名を馳せる知里ゆきえは不敵な笑みを浮かべた。
寡黙な者もいれば大らかに笑う者もいたが、18人のラーメン神たちは一徹がどれほどのことを成し遂げたのか一瞬で見抜いた。いや、嗅ぎ抜いた。弟子(元アルバイト)の成長は当然喜ばしいし、何よりも一徹のことを誰もが応援していたが、誰にも負けるまいと凌ぎを削って生きてきた者達であるがゆえ、強敵の登場を予感して険しい顔つきにもなるのだった。
「本日はわざわざお呼び立てしてしまったこと、申し訳なく思っております。さ、さ、ジジイのあばら家ゆえ、洒落た気配のカケラもありません。テーブルも椅子もないこと、ご容赦ください。さ、さ、ゴザの上にお座りになって、しばしお待ちくださいませ。今、麺を茹でて参りますので。」
一徹は師匠達に深々と頭をさげると、ボロボロの暖簾をかき分けて奥に下がった。奥の方に大きなかまどがあるのが見えた。師匠達は互いに様子を見合っていたが、最初の一人がゴザに腰を下ろすと、あとは順々にそれに習った。日本全国ラーメン戦争、常日頃は血で血を洗う抗争の大将同士である神々が、ちいさなささくれ立ったゴザの上に所狭しと座っているのは、異様な光景だった。これから食わされるのはどのようなラーメンなのか、その緊張感で、誰も口を聞くことがなく、あばら家にはただただ、暖簾の向こうで一徹がラーメンを完成させる音だが鳴り響いていた。
しばらくすると一徹がラーメンを運んできた。とは言え、18人分を同時にというわけには不可能だ。まずは1杯のラーメンが運ばれてきた。
師匠達はその器を見て目を疑った。なんだ!なんという美しいラーメンなのだ!その場にいる誰もが、真に崇高なラーメンというのは見た目の上でも並々ならぬ輝きを持つことを知っていた。だがしかし、これはどういうことだ!目の前にあるラーメンは、絶世の美麺、スープは世界のどんな湖よりも美しく輝き澄み渡り、言うなれば銀河系を丸ごとどんぶりの中に沈めたようだった。ルーブルだか大英だかわからぬが、世界のどんな美術館に貯蔵されている重要文化財のどのものよりも、その一徹のラーメンは美しかった。
そして、匂いだ。嗅覚というものは視覚や聴覚よりも動物の本能に直結しているという。様々なアロマや香水の類がこれほどに世界中で発達しているのが何よりの証拠であるし、求愛行動にもっとも重要とされるフェロモンの正体が匂いであるということが昨今では解明されている。しかし、絶対的な美匂というものは存在しない。全ては相性の問題で、人それぞれ好みの匂いは違う、というのが定説である。しかしだ。一徹の運んできたラーメンどんぶりから漂うそれは、そんな次元をゆうに超えていた。絶対的美匂!!人類、いや、世界のありとあらゆる生物を口説き落とせるであろう匂い。フと気付くと、外が騒がしい。近所の野良猫や野良犬が集まってきているのだ。窓から外を見ると、おびただしい数の鳥達が部屋の中に入ることを望んでいた。
そこにいる師匠達の誰もがこれまでに何千杯というラーメンを食べてきた。職業病というべきか、いつしかラーメンへのウブな気持ちなどとうに忘れたつもりだが、一徹のラーメンを前にした瞬間、誰もが頭の中が真っ白になっていくのを感じていた。グーーーー。巨大客船の汽笛かと聞きまごうほどの轟音を、18の腹が喘いた。神々は、生まれて初めての母乳を前にした赤子のようにゴクリと舌なめずりをした。
「すみません、台所が狭いもので、まずは1杯になってしまいました。すぐに残りも持ってきます。どなたからでもいいので、麺が伸びてしまう前に適当に食べ始めていてくだ・・・」
一徹が言い終わるまで待てる者などただの一人もいなかった。18人のラーメンの神々が、たった1つのどんぶりにヘッドスライングをした。
ズズズズズズズズ・・・・・!!!!!
ズルズルズルズル・・・・・・・・・・!!!!
一つの丼を中心に口をつけ、360度に寝そべるように犬食いをする人々。真上から除けばさながらガーベラの花のように見えたのかもしれない。スープをすすり、箸さえ持たず、誰もが熱いスープの中に指を突っ込み麺をすくい食っていた。
「し、師匠!?みなさん!どうなさったのですか?」
一徹は驚いて腰を抜かしてしまったが、誰も答えやしない。誰もが口も聞かぬままラーメンを貪り食い、啜りあげ、瞬く間にどんぶりは空になってしまった。
「一徹!!はやく!はやく残りを運んでこい!いや、頼む、後生だから、運んできてくれ!!!!」
師匠達は頬を赤らめ、目には涙を浮かべていた。
「へ、ヘイ・・・!!」
一徹は大急ぎで台所へと引っ込んでいった。
師匠達は興奮覚めやらぬ様子でゼーハーと呼吸をあらげ、感動で焦点の合わなくなった視界で世界を眺めながら、先ほどのラーメンの味を思い出していた。思い出しただけで、全身に電撃が走り、また、感情がこみ上げた。幼い頃からの思い出が走馬灯のように頭を駆け巡り、やがて自分が今どこにいるのかさえ見失い、大いなる宇宙を感じながら幸福に包まれた。ラーメンの神々はやがて互いに目を見合わせた。
ふふ・・・
あははは・・・・
くっくっく・・・
神々は笑い始めた。笑いが止まらず、涙が止まらなくなり、お互いにきつく抱きしめ合った。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一徹のラーメンは瞬く間に全国に名を轟かせた。それもそのはずである、日本を代表するラーメン屋達がこぞって公の場で絶賛したのだから。
師匠達は祝儀として巨額を出資し、一徹のための店を創ると申し出たばかりか、誰もが自分の店を閉めて、一徹のラーメン屋を手伝いたいとまで言ったのだが、師匠達全員のラーメンを尊敬していた一徹は丁重に断りを入れた。一徹は別段大きな店を構えるでもなく、元のあばら家で、一日に可能なぶんだけラーメンを創り、訪れた人々に提供することにした。
「老い先の短いジジイでございます。私は、師匠たちに認めていただける、自分でも納得のいくラーメンを創ることができたことで満足なのです。」
しかし、一徹のラーメンを求める人間は日に日に数を増やし、十日も経つ頃には連日連夜、県境まで伸びるような行列が伸びるようになった。
一徹はラーメンに1杯640円という値段をつけていたが、訪れた者たちは感激し、一徹がお願いですからと断るのも無視して何万円や何十万もの金額を勝手に店に置いて帰った。みるみるうちに一徹は巨額の富を手に入れてしまった。
一徹がついにラーメン屋を持ったという情報を聞きつけて、これまでに一徹にラーメンを馳走になったことのあるホームレスたちが全国津々浦々からみんな一徹の元へと集結したのである。新幹線代のない者は徒歩での長旅を経てようやくたどり着き、だがしかし手には640円を握りしめている。「お代はいりませんよ」と一徹が申し出ても、「例えてめえの葬式代をケチろうとも、俺たちは一徹ちゃんのラーメン代だけはてめえで銭払って食いてえんだ」と言い張った。一徹は彼らからありがたく640円を受け取り自身のラーメンを贈った。ホームレスたちは大泣きをしながら感謝を告げ、「もう一度頑張って生きてみせる」と一徹に宣言した。一徹のラーメンが、精神を奮い立たせたのである。一徹は、金持ちたちが置いていった巨万の富を、彼らにくれてやることにした。ホームレスたちは感謝の印にと、どこから持ってきたのか木材などを用いて、あばら家の周りの荒れ果てた土地に、立派な建物を立ててしまった。これには一徹も断ることをしなかった。すると、待ってましたとばかり日本国内中の要人がこのプロジェクトに力を貸し始めた。こうして、巨大ラーメン施設「あばら家ラーメン一徹」が完成したのである。あくまで巨大なあばら家の様相を守った外面ではあるが、その広さは、某テーマパークにも匹敵するほどになった。一徹の元で一徹を支えるホームレスたちの数は400人にも及び、みな有能で立派な従業員へと生まれ変わり、一徹ラーメンの爆進の重要な戦力となったのである。
「あばら家ラーメン一徹」は、今や世界中から観光客や政府の要人が訪れるスポットとなってしまった。
食べた者同士が絶対に仲良くなってしまうPeaceful Foodだ、とロイター通信の記者が書いたことも火付け役となり、平和の食べ物として世界中の人間の知るところとなった。北朝鮮総書記とアメリカ大統領の会談が開かれる際には、あばら家ラーメン一徹が会談場所として選ばれた。核戦争前夜の緊張感の中で繰り広げられた会談だったが、熱いラーメンを啜りあった両国首脳は大笑いの元に握手を交わし、今後一切互いが互いの不利益になることはしないと硬く誓い合った。
この年、一徹は紫綬褒章を賜り、数々の文学作品や映画でも一徹のことが題材となった。山田洋次監督作品「令和の麺仙人」がカンヌ映画祭でパルムドールを受賞したのは3年後のことである。
しかし、栄枯盛衰、盛者必衰の理から逃れることは一徹にも不可能であった。あばら家ラーメンが世界を騒がすようになってわずか一年ほどのある夕方、一徹は店の厨房で倒れたのだ。一徹の体を脅かしていた病魔は月日とともに残酷な力を増し、今では一徹の命を奪おうとしていたのである。
一徹が倒れると、従業員たちは即座にその日の営業を中止し、必死で看病をした。一徹が倒れたニュースは世界各国で報道され、誰もが一徹の回復を祈った。
「私のことは大丈夫ですから、みなさんお休みになってください。」
一徹は、夜は独りで眠りたいからと、夜通し看病することを願った従業員たちを部屋から出した。一徹の寝室は昔から変わらぬまま、あのあばら家の居間だった。ここだ、この場所にゴザを引いて、師匠たちに自分のラーメンを召し上がっていただいたのだ。幸せだ。この一年はまるで夢を見ているようだったなあ。あばら家の荒れ果てた天井を見上げながていると、一徹は思わず笑いが込み上げてきた。
次の日の明け方、従業員が一徹を起こしにあばら家を訪れると、中はもぬけのからだった。
一徹は、どこかに消えてしまったのである。