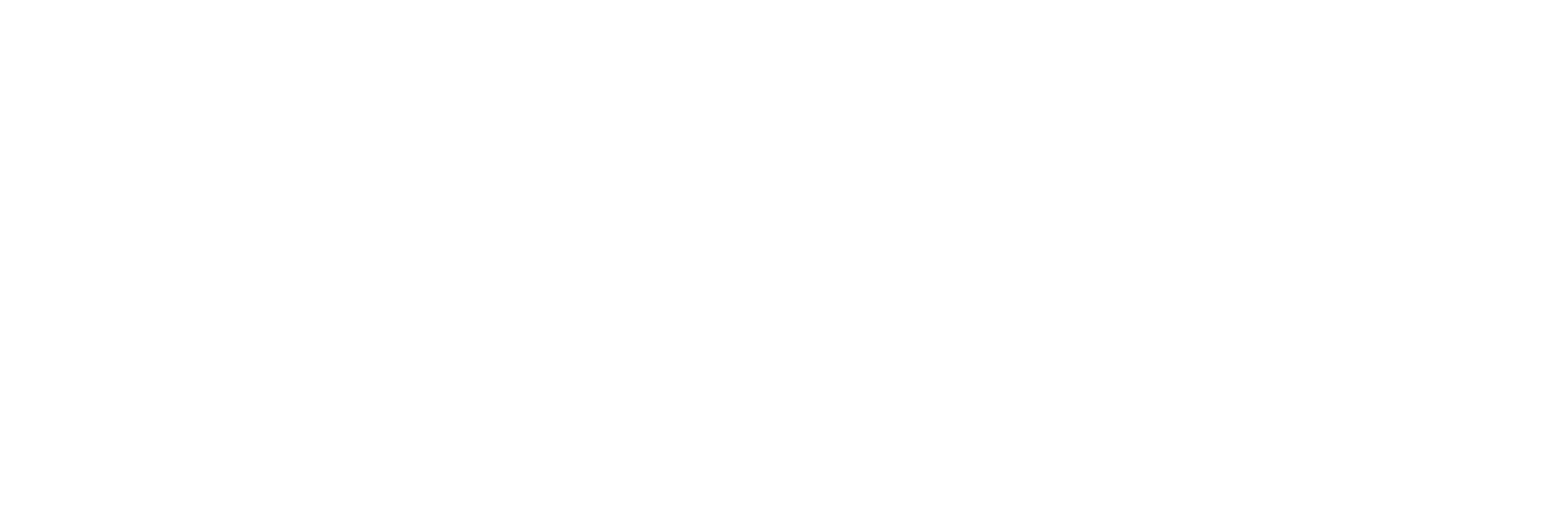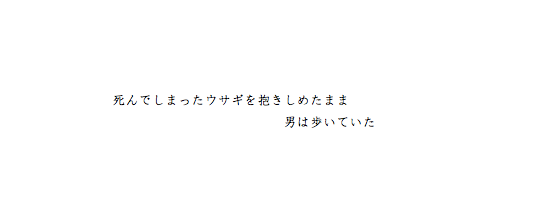ウサギが死んだ。
男はその死体を盗み出した。この陰鬱なる盗難の被害者はウサギだ。ウサギは、自分の飼主であった男から、死体を盗み出されたのだ。
死んでしまったウサギを抱きしめたまま男は歩いていた。
ウサギは突然死んだ。しかしどういうわけだろう。不思議なことに男は、ウサギが死んだ瞬間のことをどうにも思い出せないのだ。いつ死んだのか?気付いたら死んでいたのである。もしかすると、もう随分と前から命は尽きていたのかもしれない。だが、男は心底このウサギのことを愛していたし、心の拠り所にもしていた。それはそれは大切にしていた。だからきっと、ウサギの死には気が付かなかったのだろう。
あれ・・・
と思った瞬間は心臓が凍りつきそうになった。ある夕方のことだった。すぐに男は独り言を言った。「血の気が引くというのはこんなことかぁ。なるほど、本当に、血の気が引くのだなぁ!」。男はウサギの死を冗談に仕立てようと躍起になり、なるべく不真面目に不誠実に死と向き合った。「死」という厳かな事態も、こちらが茶化し続ければきっと怒って退散をするのではないだろうか、と考えたのである。
男は散らかりきった部屋のゴミの山をかき分け台所まで行くと、食べかけで置いてあったポテトチップスの袋を手に取った。男は死んだウサギを抱きかかえると膝の上に乗せて座り、テレビの電源をつけた。なるべく低俗なバラエティ番組にチャンネルを合わせると、ポテトチップスの袋の中をガサゴソとあさった。「あ、思ってたより残り少ないじゃんかぁ。ちょっとしっけてそうだなぁ!」
ポリポリポリポリ
男はゲラゲラと笑いながらポテトチップスを食べウサギの死体を撫でながらテレビを見た。バラエティ番組はやがて終わり別の番組になったが、男はチャンネルも変えずにテレビの前に座り続けた。いつのまにかテレビ画面が砂嵐に覆われた。その日の番組プロジェクトがすべて終わったのだろう。ザーーーーという砂嵐の音を聞きながら、男は思い出し笑いをしていた。何を思い出しているのかはわからなかったが、何かを思い出していた。あまりに笑いすぎて涙が出てきた。砂嵐を見つめながら男は涙を流して笑い続けた。
死んでしまったウサギを抱きしめたまま男は歩いていた。
気付いたら歩いていたのである。これまた不思議なもので、男はどうしてそんなことをしているのかは覚えていなかった。自分の身なりを見れば、しっかりとコートを羽織っているし靴も履いていたので驚いたものだ。いったいどれほどの間歩いているのか思い出そうにも思い出せないのだが、特に疲れもなく、どこを目指しているのかも定かではない。男は死んでしまったウサギを大切そうに抱きしめ、ただただ歩き続けていた。
コートのポケットにカセットウォークマンが入っていたので、イヤホンを耳につけ、機械のスイッチをオンにした。かつて友人にダビングしてもらったカセットで、その曲たちの名前を男は知らない。自分でもその音楽が好きかどうかわからなかったが、カセットをほとんど持っていない男はこの音楽を繰り返し聴くしかなかった。「音楽を聴きながら街を歩くと、まるで映画の冒頭場面みたいだな」と男はいつも思った。素敵な音楽とともにカメラが街並みを映して行くという映画でおきまりのオープニングが、男は好きだった。「これからここで、どんな物語が始まるのだろう」という気持ちになる。耳が音楽で満たされ感覚が鋭くなったのだろうか。嫌な匂いが鼻をつくのに気が付いた。
「わ。目玉とか、ドロドロじゃないかよお」
ウサギの死体は醜く腐り始めていた。
男は「生き物というのは火葬した時の姿のまま天国に行くのだよ」という祖母の話を誠に信じていたので、早くウサギの亡骸を火にくべてやるべきだと思った。だがしかし、歩み続ける足が止まらない。まあいい、このまま夜が明けたら、その時この死体を燃やせばいい。夜が明けるまでだ。朝が訪れたら。とりあえず今はこの腐ったウサギの死体を抱きしめながら歩き続けるのが良い気がするぞ。
「ごめんな、もう腐り始めちゃって、お前きっと、天国行くときにはゾンビだな。ハロウィンの時だけは大人気だろうな。」
男は抱きかかえたウサギの死体に向かって話し続けた。イヤホンから聞こえる音楽は明るいメロディの曲に変わっていた。
かちゃ、という音とともにカセットテープのA面が終わると、男はテープをひっくり返してB面を再生した。B面もすぐに終わるもので、男は再びテープをひっくり返す。気が遠くなるほどの回数それを繰り返した頃だろうか、気がつくと男は海辺の断崖絶壁に立っていた。自分の街に海があったことなど初めて知ったが、それなりに遠くまで歩いて来たのだろう。
男は自分自身では気付いていなかったが、背中がすっかり曲がっていた。髪の毛はもはや真っ白で、顔はしわくちゃだった。衣服はボロボロに風化していて、腕に抱えたウサギは真っ白な白骨に変わっていた。
「ほーら、ミステリードラマの最後、犯人が追い詰められそうな断崖絶壁だぞ。有り体に言えば、絶体絶命だ。よし、配役を発表する。追い詰められる犯人は俺で、お前は追い詰めている刑事さんだ。」
男はウサギの白骨死体を、崖の先端から少し離れた地面の上に置いて海側を向けた。男はイヤホンを外しウォークマンごと海に投げ捨てると、絶壁ギリギリのところにまで歩いて行き、白骨化したウサギの方を振り返った。ザバーンザバーンという潮騒の音があたりを包んでいた。いつだか聞いたテレビの砂嵐の音に似ているな、と男は思った。
「そうさ!こうなったら何もかも白状するぜ。お前の言う通りだ・・・俺が盗んだのさ。お前の死体を盗んだのは、俺だ。だがしかし手遅れだな。お前の大切なお前の死体は、もう真っ白な骨になっちまった!」
男は大きな声で笑い出した。ウサギの白骨死体のことを見つめ、ただひたすら笑っていた。
「さあ、どうする・・・?人は見た目が九割というぞ。ウサギの場合だって似たようなものだろう、九割とまではいかないかもしれないが、八割・・・いや、七割くらいは見た目で判断されると思うぞ。いいのか?そんな姿形で天国に行ってみろ、第一印象で随分損するぞ!本当に行くつもりか!?」
ゲラゲラと品のない声をあげて笑っていたものの、男は驚いた。自分が涙を流していることに気が付いたからだ。潮風というのはこれほどに目にしみるものなのか、それとも、寒さが厳しすぎるせいなのか。
やがて男は声を失った。喋ろうと思ってもどうにも声が出ず、ヒューヒューと風のような音がするだけ、笑い声のひとつも出すことができなくなっていた。男の喉から漏れ出るヒューユーという音はあたりの風の音に混ざり続けた。
男は、真っ白で細い姿になった自分のウサギの元まで歩いて行くと、ひざまづいた。じっくりと見つめてみると、それはそれは美しく思えた。そのことを伝えたかったし、「ああ、せめて話してくれたら良かったのにな」と冗談めかして言いたかったのだが、男の喉からは相変わらず風が吹きすさぶだけだった。
男は震える手を伸ばし、大切な大切なウサギに触れた。その瞬間、白骨化したウサギの骨は、パリンと高い音を立てて、薄いガラスがはじけるように砕けた。全ての骨は透明な白い粉の山になった。崖の上の風たちが白い粉となったウサギを盗み出そうとしたので、男は身をかぶせて守った。その粉を一粒残さずすくい上げようとしたところ、両の手のひらだけでじゅうぶんに事足りた。さざなみの音と風の音が混ざり合っていた。男は、ウォークマンを捨ててしまったことを少し後悔した。映画を観るとき、物語の最後の場面が終わった瞬間にエンドロールとともに流れる音楽がとても好きだったからである。
空を見上げてみた。どうやら朝は訪れそうにない。消えてしまいそうな三日月が雲の隙間から顔を覗かせていた。男は、手のひらいっぱいにすくい取った白い粉末を飲みこみ始めた。液体を飲むようには簡単に成し遂げられず、口の中はジャリジャリとしたが、飲み干し続けた。すべてを飲み終えてしまう頃、男の体もまたパリンと音を立てて白い粉の山になった。吹きすさぶ風は、長い時間をかけてその粉を海へと運び、そして海の底へと沈めるのだった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
浴槽で男の死体を発見したとき、借家の大家は随分と憤ったものだ。
いわゆる孤独死と言うもので、近隣住人からの「異臭がする」と言う抗議を聞いた大家が合鍵を持って部屋に入ると、部屋の中はゴミの山。ハエがブンブンと飛び交い、目にしみるような悪臭が立ち込めていた。つけっぱなしのテレビはザーーーーという音とともに砂嵐を映しているだけだった。住んでいるはずの男の名前を呼んでも返事がなく、やむを得ないので大家は土足のまま部屋の中に押し入った。浴室の扉を開けると、湯を張った浴槽の中で男は死んでいた。死後数日が経っていた。浴槽の様相は惨憺たるもので、腐敗した肉体は溶け出して、湯船を赤黒く染めていた。男の体は、目を覆うほどに醜く腐敗していた。
「畜生め!」
大家は叫んだ。そして不思議に思った。
浴槽の中で死んでいる、もはや白骨化が始まっているその男が、ウサギのぬいぐるみを抱きしめていたからである。