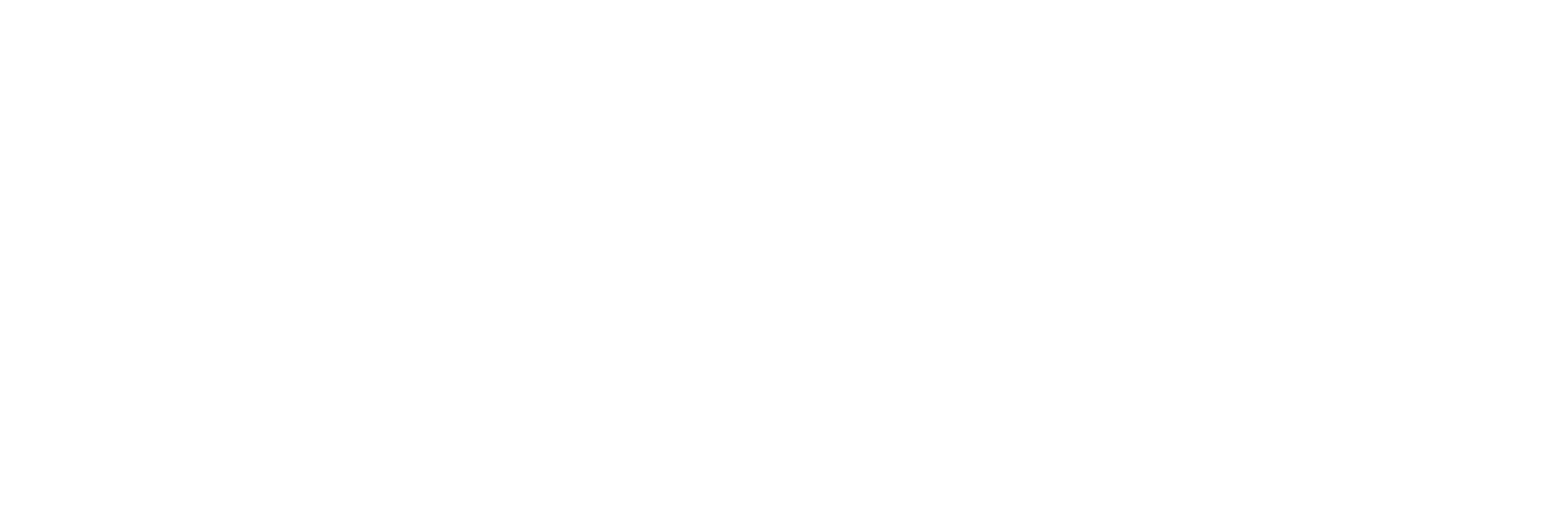手紙を綴ることを禁じられて、老人は戸惑った。「お願いですから綴らせてください、決してその手紙を出したりはしませんから」と懇願したが、許してはもらえなかった。
老人は若い頃からひたすらにその千鶴華(ちづか)という女に向けての手紙を綴り続けていた。なんと驚くべきことに、それは千鶴華が生まれてくる前からのことだった。ある日、まだ少女だった千鶴華の元に老人が訪れ、荷車いっぱいに積んだ手紙を見せて言った。
「ようやく出会えました。これは、あなたが生まれてくる前からあなたのために綴り続けてきた、私からの手紙です。」
千鶴華は気味悪がり、召使いを呼んで男を追い払った。高貴な生まれだったのである。しかし、また何ヶ月かすると、老人は千鶴華の元を訪れ、大量の手紙を見せた。その都度、召使いたちが老人を追い払った。そんなようなことが、10年も続いたのである。千鶴華は今ではもう、立派な大人の女になっていた。老人は変わらぬまま、老人であった。
千鶴華はやがて、若い男と恋に落ち、祝言を挙げることになった。そこで、老人を呼び出すと、「もう今後一切、手紙を綴ることを辞めてほしい」と告げた。しかし老人はそれだけは勘弁してくれと頭を惨めに上げ下げするのだから、千鶴華は困り果ててしまった。
「あなたがいつもどこかで私を想って手紙を綴っていると言うことが、私を苦しめるのです。申し訳なさに胸が痛むのです。なぜなら私はあなたを大嫌いなのですから。」
「私のことを思いやってくださると言うならば、私は、手紙を綴ることができないことの方が余程に辛いのです。どうしてもあなたに手紙を綴りたくて、そうでないと自らの胸の内にある思いが膨れ続けて破裂して、私は死んでしまいそうになるのです。後生ですから、誰にも見せませんし、綴ったらすぐに破り捨てて火にくべるので、あなたに手紙を綴ることを許してください。」
しかし、願いが聞き入れられることはなかった。
「あなたが苦しいのは、手紙を綴り続けてしまうからなのです。綴るのを辞めてしばらくすれば、きっとあなたは救われますから。絶対に、大丈夫ですから。」
千鶴華は言い放った。
老人が持つ紙と筆のすべて火にくべて燃やされ、町中の者たちは、誰も老人に紙や筆を与えてはいけないことになった。老人は今後一切、千鶴華への手紙を綴ることを禁じられ、その禁を犯せば罰せられることになったのだ。
しかしほどなくして、老人が手紙を書いているのが見つかった。雨の日のぬかるんだ地面に、木の棒を用いて千鶴華への想いを記していたのである。
当然、老人は罰せられることになった。役場に呼び出された老人は、もう二度と手紙を綴ることができないようにと両腕を切り落とされてしまった。切り落とされた両の腕を置いて、老人は立ち去った。老人の傷跡から滴り落ちた血液が、鮮やかな赤い道を浮かび上がらせていた。人々はこれでようやくすべてが解決すると胸をなでおろした。
しかしほどなくして、老人が手紙を綴っているのが見つかった。雪の降った朝に、足で雪にあとをつけ、千鶴華への思いを綴っていたのである。それは、巨大な巨大な白く輝く手紙であった。
当然老人は罰せられることになった。役場に呼び出された老人は、もう二度と手紙を綴ることができないようにと、両足を切り落とされてしまった。老人は切り落とされた両の足を置いて立ち去ろうとしたが、手も足もない老人はごろごろと転がり回ることしかできなかった。役人は荷車の荷台に老人を乗せ、老人の住む狭い小屋まで送り届けることとなった。人々はこれでようやくすべてが解決すると胸をなでおろした。
老人は狭い小屋で身動きもせずに暮らすことになった。千鶴華は召使いに言いつけて老人の身の回りの世話をしに通わせた。それからしばらく、誰も老人が手紙を綴っているところを見かけなかった。それもそのはずである。手も足もないのでは、手紙など綴ることのできようはずもない。
千鶴華は、老人が自分に抱いていた恐ろしいほどの執着が解けたのだと考えて、ある晩、人目を忍んで独り老人を見舞った。
「私はあなたのことを疎ましく思っていますが、両手と両足を切断してしまったことは悪かったと思っています。かつてあなたはまるで呪いにかかったように私のことを思っていたようですが、それも過去のこと。手紙を綴ることができなくなってからと言うもの、あなたは少しずつ呪いから解放されたのですね」
「いいえ。それが、本当に申し訳ございません。私は今でも、手紙を綴り続けてしまっているのです」
驚いた千鶴華が、どう言うことですか一体どこに?と尋ねると、老人は目を閉じて言った。
「ここです。頭の中です。頭の中に、あなたへの手紙を綴り記しているのです。毎朝毎晩、続けました。いえ、毎秒、あらゆる刹那に、私は、あなたへの思いを書き綴っています。そしてその全ての言葉を、今でも諳んじてあなたに読み上げて見せることができます。」
千鶴華は激昂して言った。
「今すぐにお辞めください。頭の中で綴ることも許すことはできません」
「だけど、できないのです。どうしても、どうしてものことなのです」
「それでは・・・両手を奪い、両足を奪っても無理だと言うのであれば、次は首をはねてしまえばいいのですか?」
「それでも構いません。お願いです。どうか、後生ですから、この通りですから許してください」
手足を持たない老人は泥だらけの床に顔面から伏して懇願したが、しかし、千鶴華は許せないと断じた。
老人は青ざめ、年甲斐もなく泣きわめき始めた。しかし、遂には千鶴華の求めに応じ、もう金輪際、手紙を綴ることも、その言葉を思い浮かべることもしないと誓った。
数日後に、老人は死んだ。死んだ理由は誰にもわからなかった。
千鶴華は、召使いからその報せを受けて、大きな声をあげて泣いた。