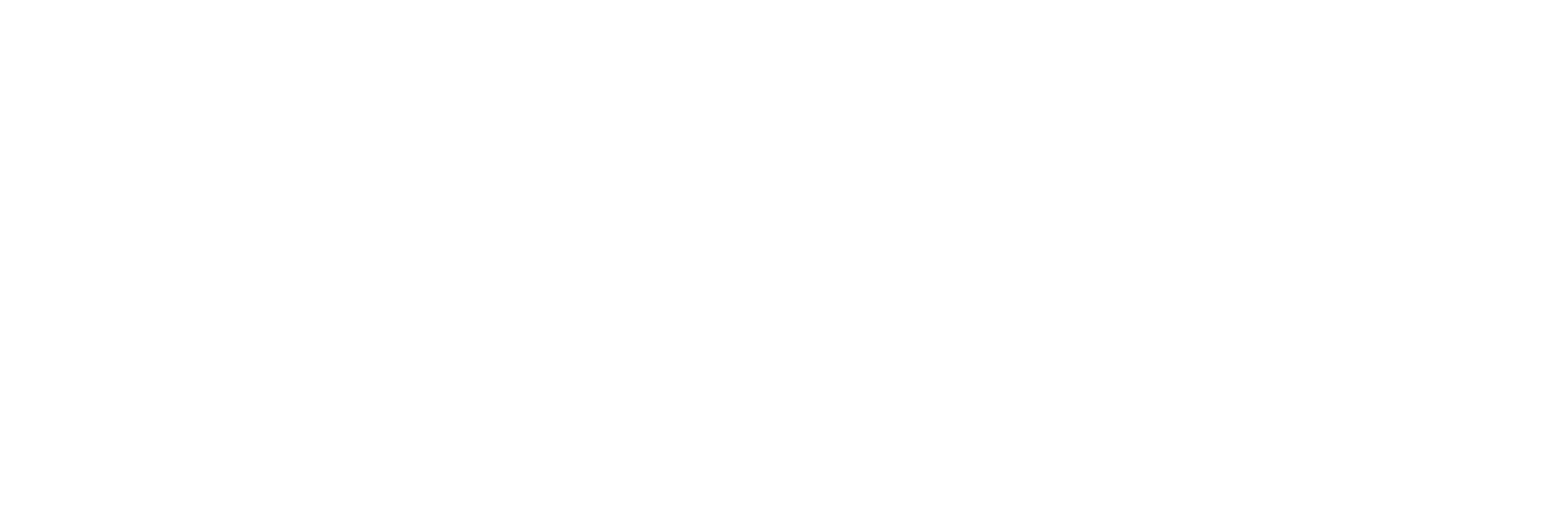りんごが木に実っている。二人の人間が木の下までやってきて、りんごを見上げていた。りんごは、人間には男と女という二つの種類があって、また、100年近くも生きる動物なのだということを知っていたけれど、歩いてきたふたりがどういう人間の類なのかはわからなかった。
甲「あんなに赤くなるなんてよほど自分に自信があるのだろうけど、汚らわしい。派手すぎる。慎ましやかな精神があれば普通あんな色にはならないでしょ。」
乙「そういうもの?りんごって、そうなんだ。」
甲「そりゃそうさ。自然の味、なんて言われて調子に乗っているけれど、それは自分を売るためのポーズに過ぎないからね。本当は何もかも計算済み、極めて野心的な果物さ。いやね、わかっちゃうんだよね。ほら、見てごらんよ、あのりんごの太陽の光を受けての輝き方。あの輝き方は、周りの世界を見下してる。それにあたかも、自分が太陽に愛されています!ていう様相だ。」
乙「そうかな。」
甲「こういうのを聞いたことない?人類創世のしばらくあと、りんごの実はアダムとイヴのことを誘惑して自分を食わせ、二人を楽園から追放させたんだってよ!」
乙「でもそれは神話でしょ?それに、それ、りんごの方が誘惑したの?むしろ逃げようがなくて悲しくも食べられてしまったんじゃなくて??」
甲「だってそれまではアダムもイブも、一度だって木の実を食べたことなんてなかったんだよ??それなのに食べてしまっただなんて、明らかにりんごの方からのアプローチがあったってことでしょうが!」
乙「そうかな?」
甲「そうでしょうが!」
乙「そうだね。」
りんごは二人の会話を聞いて悲しい気持ちになった。りんごはもちろん、誰かを誘惑しようとしたことなどただの一度もないし、実が赤いのも自分で選んだわけではない。ただただ自分の生に感謝し、目一杯に成長することこそ世界への感謝だと思った結果、次第に実は大きくなり、色づいたに過ぎないのだ。もちろん、自分では自分の色や姿、そしておそらくは甘いであろうその味に関しても誇りは持っている。だがしかしそれは、たとえ形が小さく色が青く味が苦かったとしても、そうであったと思う。そういうことを、下にいる人間たちに伝えたいな、と思ったものの、りんごは喋ることができない。残念に思っていると、下からまた声が聞こえてきた。
甲「・・・ほら。りんご、何も言い返さないよ。あれだけ言ったのにさ。ここで話してたんだ、聞こえていないって方がおかしいとは思わない?」
乙「あー、まあ、確かに。」
甲「サイッテーな果実だな、りんごとか言って!あんな高いところから見下ろしやがって!」
乙「ま、まあ落ち着いてよ。」
甲「あ?なんだよ、え?りんごのこと庇うの?」
乙「いや、別に庇うとかでもないけどさ、りんごもりんごなりに、年がら年中りんごなんだしさ、それなりに考えて、必死で?腐って地面に落ちる前に食べてもらう方法、怯えながらに考えたんじゃないのかな、って」
甲「あぁ。やっぱ嫌いだ、りんご」
乙「え?」
甲「だからさ、こういうことなんだよ。こうやってな、あんたみたいなやつの同情とかをうまく利用して、いけしゃあしゃあとやってくのがりんごって果実なんだわ。普通ね、本格的な果物はそんな汚い真似しないから!」
乙「そういうものかな・・・」
甲「まあ、いいわ!こんなゴミみたいな木に成った最低な木の実、カラスに突かれるか腐って落ちるかしてしまうのがいいさ!せいぜい調子に乗ってな!行くよ!」
乙「ちょ、ちょっと待ってよ!」
二人は去って行ってしまった。りんごはその背中を見つめながらため息をついた。ここまでただ成長してきただけで、それ以上何も話していないし、考えてもいないんだけどな。随分と、賑やかな人たちだったな。どうか、あの人たちが幸せになってくれますように。